事業開発プロの新たなキャリア|2025.10.04
トヨタの新規事業の全貌とは?未来を変えるプロジェクト実例まとめ
自動車産業が「100年に一度の変革期」にある中、日本の巨大企業であるトヨタは、既存の枠組みを超えた新規事業を次々と展開しています。...
Magazine
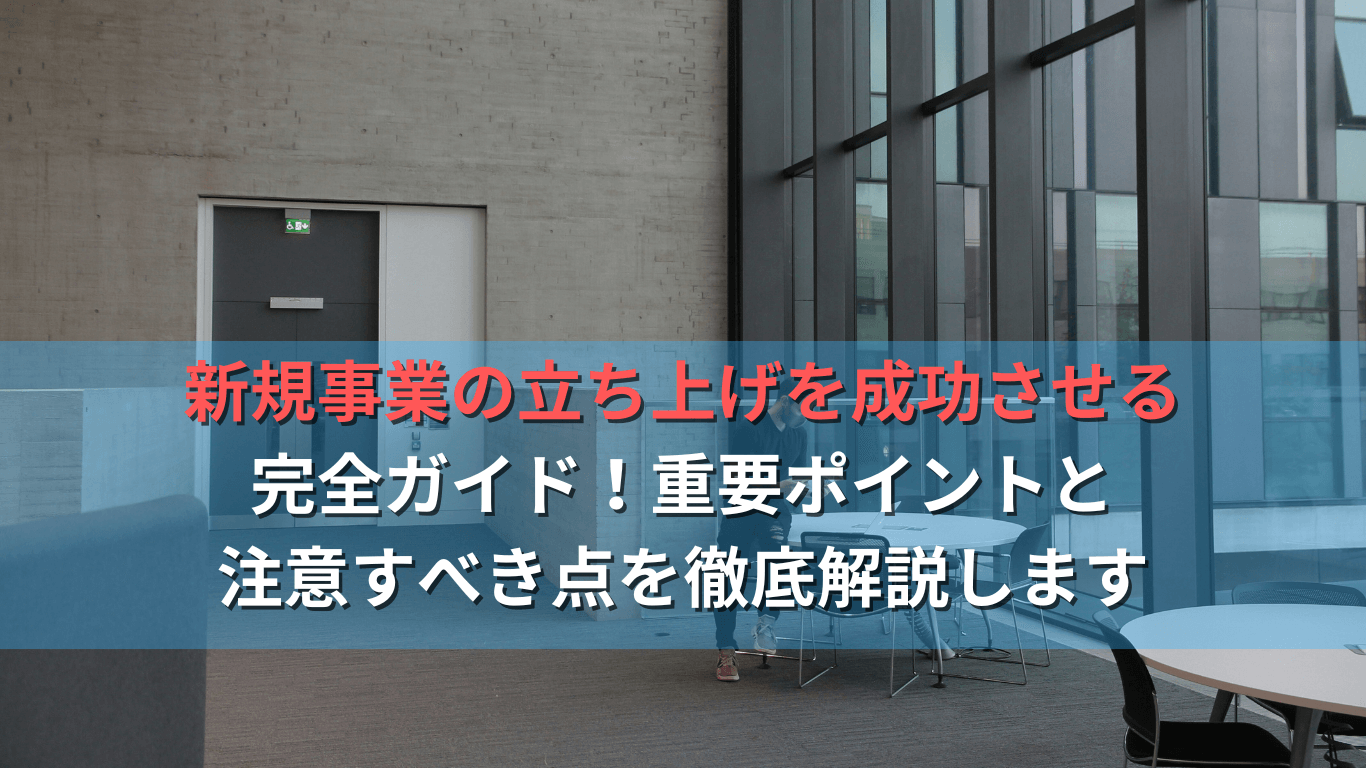
事業開発プロの新たなキャリア
2025.05.22
新規事業の立ち上げって何から始める?初めて新規事業の推進を担当することになったけど、全体の流れがつかめなくて不安…
新規事業を任されると、期待されているという嬉しさの反面、どう進めていいかわからない不安もありますよね。やみくもに動くと、他部署からの信頼を失墜させたり、準備不足でつまずくと失敗が続くかもしれません。
そこで、今回は新規事業の立ち上げの手順と成功のポイントについて紹介します!難易度の高い新規事業ですが、一定程度は型に沿って進めることもできますので、この記事を参考に、自分なりの進め方を確立してみてください。
この記事で分かること!
弊社サービスNewAceは、あなたのチャレンジを応援するコンサルタントの方向けのプラットフォームです。
案件のご紹介のほか、様々な相談も承っておりますので、是非下記よりご登録ください。

それでは、本章をチェックください。
目次

新規事業とは、既存の枠を超えて企業が新しい価値や収益の柱を創出する活動です。特に大企業においては、社会や市場の変化に対応しながら次の成長エンジンを作ることが最大の目的となります。
まずは、この基本をしっかり押さえておきましょう。
新規事業とは、これまで企業が手掛けていなかった新しい製品・サービス・ビジネスモデルを企画・実行することです。
たとえば、家電メーカーがIoT領域やBtoBソリューションに挑戦する、物流会社がITプラットフォームを立ち上げるなど、事業の軸をずらす動きが活発です。
新規事業は「新しい収益源を作る」「将来の主力事業を生み出す」ために不可欠な戦略と言えます。
大企業の新規事業には以下のような特徴があります。
たとえば、既存事業は「安定した収益」や「効率化」が重視されますが、新規事業は「柔軟な発想」や「スピード感」「市場への適応力」が必要です。
組織の壁や縦割り体制を超えた連携も成功のカギとなります。
新規事業と既存事業の最大の違いは「不確実性とリスクの高さ」です。
たとえば、既存事業は過去のノウハウや実績がベースですが、新規事業はゼロからのスタート。現場でのトライ&エラーや、柔軟なピボット(方向転換)が求められるのが大きな違いです。

なぜ今、多くの企業が新規事業に力を入れるのでしょうか。市場環境の変化や企業成長のため、新規事業の重要性は年々高まっています。
これら3つの観点から、背景と理由を整理します。
新規事業は、変化が激しい市場での競争力維持・強化に直結します。
たとえば、大手メーカーが既存製品の売上低迷を受け、新領域に進出するケース。IT・AI技術の台頭やスタートアップの急成長など、今ある強みだけでは生き残れない時代になっています。
新しい事業を生み出すことが、会社全体の「生存戦略」となります。
新規事業は、次世代リーダーやイノベーター育成の場にもなります。
たとえば、新規事業プロジェクトに手を挙げた若手が、数年後には経営幹部に抜擢される例も増えています。
「自ら考え動く」「失敗から学ぶ」経験が人材育成や組織活性化にも大きく貢献します。
企業が持続的に成長するには、新たな収益源や市場の開拓が欠かせません。
たとえば、グローバル化や人口減少など、外部環境の変化に強い組織を作るためには新規事業の積極投資が重要です。
攻めと守りのバランスを取りながら、会社の未来を切り拓く役割を担っています。

新規事業の立ち上げは、偶然のひらめきだけでは成功しません。実践現場で有効な「8つのプロセス」に分けて、具体的な進め方を解説します。
これらのプロセスを1つずつ丁寧に進めることが、成功への近道です。
新規事業の第一歩は、「どの領域・分野で勝負するか」を明確にすることです。
たとえば、社内に眠る技術や知財、既存顧客基盤をベースに事業領域を絞り込む。この段階で曖昧なまま進めてしまうと、後で「なぜこの分野なのか?」と組織が迷子になりやすいです。
自社の強みと市場ニーズの交点を探し、経営陣・現場の合意を得て方向性を固めましょう。
「なぜ新規事業をやるのか?何を目指すのか?」を明確に定義することが重要です。
たとえば、「5年後に●億円の新規売上創出」「業界トップのシェア獲得」など、定量・定性的な指標を設定。ビジョンや目標が曖昧なままだと、プロジェクト推進力や社内の巻き込み力も低くなります。
最初の段階で「目指す姿」を鮮明に描くことが、新規事業推進の原動力になります。
次に、「どんなアイデアや顧客課題を起点にするか」を考えます。
たとえば、既存顧客の声をヒアリングして潜在ニーズを抽出したり、全社でアイデアコンテストを実施する。社外のスタートアップやベンチャーとの協業から新しい着想を得ることも有効です。
この段階では「発散と集約」を繰り返しながら、本当に解くべき課題・面白い種を見つけます。
アイデアを「本当にビジネスになるのか」を客観的に調べる段階です。
たとえば、ターゲット顧客にヒアリングやアンケート調査を行い、支払意思やニーズのリアルを把握。プロトタイプを作り、実際にユーザーに触ってもらうなど小さな検証を重ねることで、机上の空論を排除できます。
この段階で「やるべき理由があるか」「儲かる見込みがあるか」をしっかり見極めましょう。
市場検証で一定の手応えがあれば、いよいよ「具体的な製品・サービスを形にするフェーズ」です。
たとえば、最初から完璧なものを作ろうとせず、「早く出して早く直す」マインドが重要です。社内外のメンバーやテストユーザーと密に連携し、「現場の声」をプロダクトに反映。
ここで大きな投資やリソース配分を決める場合は、意思決定プロセスの透明化も欠かせません。
新規事業は「ヒト・モノ・カネ」すべての調達と組織設計が成否を左右します。
たとえば、資金が潤沢な大企業でも「新規事業への予算配分」や「専任体制構築」は毎回の大きな課題。スタートアップ的な少人数組織を社内に作る企業も増えています。
「事業推進に集中できるチーム・環境づくり」が成果につながります。
良い製品やサービスができても、「売れる仕組み」や顧客獲得戦略がなければ成功は遠いです。
たとえば、ITサービスならリリース直後からWeb広告やオウンドメディア運用を強化。パートナーや販売代理店を活用して顧客獲得を加速する手法もあります。
「どのように最初の10人、100人を獲得するか」のプランが明確なほど成功確率が高まります。
最後のステップは、「実際に事業が動き始めてからの評価と改善、そしてスケール戦略」です。
たとえば、毎月の数字をもとにPDCAを高速で回し、改善点をすぐに実行。ヒットした後の「拡大戦略」や「新規市場進出」を見据え、段階的に事業規模を大きくしていきます。うまくいかない場合は、早めにピボットや撤退判断も必要。
「完璧な成功」よりも「柔軟に修正し続ける」姿勢が新規事業成功の鉄則です。

新規事業を成功させるためには、「どんな人材・スキルを揃えるか」が大きな分かれ道となります。既存事業とは異なる能力や個性が集まることで、革新的なアイデアと推進力が生まれます。
この5つの能力はどの業界・業種でも必須です。
新規事業担当者には圧倒的な情報収集力が求められます。
たとえば、毎朝必ず業界ニュースや競合動向をチェックする、現場の声を直接ヒアリングする習慣がある人は強いです。「知らなかった」「調べなかった」は新規事業の失敗原因No.1と言えます。
顧客や現場の「まだ誰も気付いていない課題」を発見する力が新規事業の原点です。
たとえば、「顧客が本当に困っているのはどこか?」「現場の作業で無駄になっているのは何か?」を粘り強く探る力が差別化の原動力になります。
新規事業は曖昧な課題を論理的に整理し、道筋を立てて実行する力が不可欠です。
たとえば、アイデア出しから事業モデル構築、改善策まで一貫して「なぜ?」「どうすれば?」を明確にすることが、プロジェクトの成功率を高めます。
新規事業は社内外への「巻き込み」「説得」スキルが成否を左右します。
たとえば、どれだけ良い事業案でも、伝え方ひとつで承認が下りない、仲間がついてこないケースは多いです。ストーリー性や熱量、データの裏付けを意識した「伝える力」が大切です。
最後は「全体をまとめて推進する力=プロジェクトマネジメント」です。
たとえば、複数の部門や外部パートナーが絡む大企業の新規事業ほど、この能力がものを言います。
「やりっぱなし」や「決めっぱなし」ではなく、最後までやり切るリーダーシップが欠かせません。
新規事業は「どんな戦略タイプを採用するか」によって、進め方や成功パターンも大きく変わります。ここでは代表的な4つの戦略と進め方を整理します。
自社の強みや目標に合わせて最適なアプローチを選びましょう。
既存の製品・サービスを新しい市場や顧客層に展開する戦略です。
たとえば、国内限定だったITサービスを海外市場に展開する、BtoC事業をBtoB向けにカスタマイズするなど。
市場調査と現地適応、現場のネットワーク構築が成功のカギになります。
今ある市場や顧客向けに、全く新しい商品やサービスを投入する戦略です。
たとえば、メーカーがIoTやAIを活用した新製品を開発する、既存サービスの新機能を追加するなど。
顧客ヒアリングや実験的なリリースを重ねて、早期フィードバックが重要です。
「自社の既存領域を飛び越えて、まったく新しい分野に挑戦する戦略」です。
たとえば、自動車メーカーがエネルギーや金融事業に進出する、IT企業がヘルスケア分野に新規参入するなど。
リスクは高いですが、当たれば大きな成長が見込めます。
既存市場・既存製品でシェアや売上の拡大を狙う王道戦略です。
たとえば、営業体制や広告投資を強化し、同じ市場で「競合に勝つ」ことを目指します。
新規事業初期には、既存基盤を活用した浸透戦略も有効です。

新規事業を進める上では、「思考の枠組み(フレームワーク)」を使いこなすことで、課題の整理や意思決定が一気にスムーズになります。代表的なフレームワークと活用法を整理します。
それぞれの現場で役立つ枠組みをチェックしましょう。
新規事業の「発想・企画」段階では、アイデアを広げて深めるフレームワークが活躍します。
たとえば、「SCAMPER」を使って「今あるサービスを他の用途に転用できないか?」と考えたり、ブレストで異業種メンバーの意見を集めることで独創的なアイデアが生まれます。
市場調査や環境分析には、事業機会やリスクを客観的に把握するフレームワークが有効です。
たとえば、「3C分析」で顧客像・競合・自社の強みを整理し、PEST分析で市場の外部要因を網羅的に洗い出します。事業立案の精度がグッと高まります。
「儲ける仕組み」を考える際は、事業モデル構築用の枠組みが役立ちます。
たとえば、BMCで「顧客セグメント・提供価値・収益構造」などを一枚の図で整理。新規事業の全体像や課題が可視化され、関係者とも共通認識を持ちやすくなります。
「どう売るか・誰に届けるか」を決める際は、マーケティング用の枠組みを活用します。
たとえば、「STP」でターゲット顧客や市場ポジションを明確化し、「カスタマージャーニー」で顧客接点や購買フローを描きます。これにより具体的なマーケ施策や販売計画が立てやすくなります。
事業開始後は「定期的な評価と改善」が不可欠です。
たとえば、「PDCA」で毎月の実績を振り返り、KPIツリーで成果要因を可視化。うまくいかなければOODAループを意識して「素早く動いて、素早く修正」することが重要です。

大企業では「社内の壁や複雑な意思決定」をいかに乗り越えるかが、新規事業成功のカギです。
現場で実践できるポイントをまとめます。
新規事業を進めるには、専任チームの設置や柔軟なリソース確保が不可欠です。
たとえば、現場主導の少数精鋭チームで素早く動ける体制を整える。リソース不足や社内調整の遅さが新規事業失敗の大きな原因となりやすいため、最初に体制面を固めましょう。
大企業の新規事業で最も課題となりやすいのが「意思決定の遅さ」です。
たとえば、稟議プロセスの簡素化や、一定範囲での現場判断権限を持たせることでスピードを上げる。「とりあえずやってみてから修正」するカルチャーが重要です。
新規事業は「社内外の多様なネットワーク」を活かすことでスピードと質が上がります。
たとえば、技術部門や営業部門、マーケ部門など横断的な連携でアイデアが生まれやすくなります。外部のベンチャー企業とオープンイノベーションを行う企業も増加しています。
大企業の新規事業は、「行政や外部専門家との連携」も有効です。
たとえば、国や自治体のスタートアップ支援施策、専門家との連携で技術・法務面の壁を乗り越える。社外ネットワークの拡大が、事業推進力の源になります。

実際にどのような企業が新規事業を成功させてきたのか、具体的な事例から学べるポイントを紹介します。
多様なアプローチや工夫がヒントになるはずです。
A社(大手メーカー)は、本業で蓄積したIoT技術を活用し、新しいBtoBサービスに参入しました。
このプロジェクトは「社内資産の再発見と活用」「現場主導の意思決定」「素早いプロトタイピング」が成功要因でした。現場からの課題発掘と、既存事業の強みを転用したアプローチは、多くの企業に参考となります。
B社(老舗食品メーカー)は、ヘルスケア志向の新市場に挑戦。
既存の枠を越えた「多様な人材の活用」「失敗を許容するテストマーケティング」「顧客巻き込み型開発」が功を奏しました。オープンイノベーションや越境チームによる推進は、今後の新規事業でますます重要なポイントです。
海外の大手企業では、「新規事業専用の分社化・子会社化戦略」がよく見られます。
たとえば、欧米のIT企業がAI・SaaS・ヘルスケア分野で独立した事業会社を設立。「本社の意思決定の遅さ」「既存事業とのカニバリ」を避け、ベンチャー的な柔軟性で成長した例も多いです。
新規事業の成功には、「正しいプロセスの理解と、現場での柔軟な実践」が何より大切です。
新規事業でよくある失敗を防ぐには、チェックリスト型の視点が有効です。
この7つを節目ごとに必ず見直すことで、大きな失敗や無駄な投資を防げます。
新規事業は「完璧を目指すより、まず動いて小さく学ぶ」が鉄則です。
この姿勢が、新しい事業を生み出し続ける組織文化の土台になります。
この記事を執筆した人

長尾 浩平
新規事業創出や事業戦略の専門家として、多様な業界での経験を持つコンサルタント兼起業家。
東京工業大学大学院 生命理工学研究科、および中国・清華大学大学院 化学工学科を卒業。グローバル企業において研究開発、新規事業企画、新市場参入戦略の立案、M&A支援、DXコンサルティング、営業戦略策定など、多岐にわたる業務を担当。業界を横断した豊富な経験を活かし、事業成長と競争力強化を支援する総合コンサルティングを提供。
2024年1月にVANES株式会社を創業し、企業の持続的成長を支援。変化の激しい市場環境において、戦略立案から実行支援まで一貫したアプローチで企業価値の最大化に貢献している。
人気記事
事業開発プロの新たなキャリア|2025.10.04
自動車産業が「100年に一度の変革期」にある中、日本の巨大企業であるトヨタは、既存の枠組みを超えた新規事業を次々と展開しています。...
事業開発プロの新たなキャリア|2025.10.04
「新規事業を立ち上げろ」というミッションを課されながら、 社内に新規事業の評価基準がない アイデアは出るが、事業化まで到達しない ...
事業開発プロの新たなキャリア|2025.10.02
大規模企業で新規事業の立ち上げを担う担当者の方々へ。 既存のビジネスモデルが成熟する中、次なる成長の柱を生み出すことは、単なるオプ...
カテゴリー