プロフェッショナルなビジネス用語集|2025.05.22
イントレプレナーとは?業務内容やアントレプレナーとの違いを徹底解説!
イントレプレナーって言葉、よく聞くけどどういう意味?アントレプレナーとは違うの? 「イントレプレナー」という言葉を最近よく耳にする...
Magazine

プロフェッショナルなビジネス用語集
2025.03.25
アイデアソンってよく聞くけど、それは何なの?イベントのこと?
アイデアソンって聞いたことあるけど、意味や目的までは知らないこと多いですよね。よく分からず参加すると、せっかくの経験を活かせず、ムダになるかもしれません。
今回はアイデアソンの意味やハッカソンとの違い、活用方法までについて紹介します!これを参考に、是非自分に合ったイベントに参加して、今後のキャリアの役に立ててください!
この記事で分かること!
弊社サービスNewAceは、あなたのチャレンジを応援するコンサルタントの方向けのプラットフォームです。
案件のご紹介のほか、様々な相談も承っておりますので、是非下記よりご登録ください。

それでは、本章をチェックください。
目次

アイデアソンは、短時間で多様なメンバーが集まり、新しいアイデアを生み出すイベントです。企業や自治体、教育機関などで注目される「発想の場」として、イノベーション創出や新規事業のきっかけによく活用されています。
まずは、アイデアソンとは何か?どんな場面で使われているのか?基本から順番に整理します。
アイデアソンは、「アイデア」と「マラソン」を組み合わせた造語です。数時間から数日間、さまざまな立場の参加者がチームを組み、特定テーマについて集中的にアイデアを出し合うイベントです。
たとえば「次世代教育」「地域活性」「新しい働き方」など、テーマは多様です。ゴールは「実現性を深く考える」というより、新しい発想や着想を短期間で量産することにあります。
「アイデア勝負」のイベントなので、専門知識よりも自由な発想や、多様なバックグラウンドが重視されます。
今、アイデアソンがさまざまな現場で選ばれる背景には、いくつかの理由があります。
たとえば、IT企業では「1日で事業アイデアを出し切る」アイデアソンが多く開かれ、そこから新しいプロジェクトやサービスが生まれるケースも増えています。
多様性とスピードが重視される現代に、アイデアソンは最適な手法として広がっています。
アイデアソンは、もともとアメリカのIT企業や大学の研究室などで始まりました。ハッカソンやブレインストーミングと並び、「短期間で集中的にアイデアを出すワークショップ」の一つです。
「マラソンのように集中してアイデアを生み出す」スタイルが新鮮で、多くの業界に広がりました。今ではオンラインやグローバル開催も一般的で、「多様性」と「短期間集中」の象徴的な手法となっています。
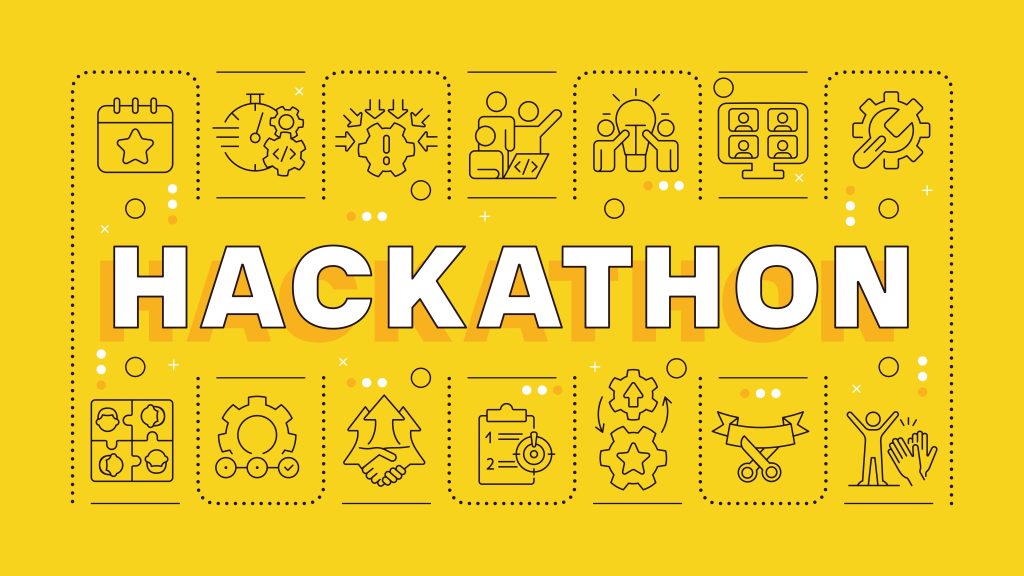
アイデアソンは「短期間でアイデアを生み出す場」ですが、ハッカソンやブレインストーミング(ブレスト)と混同されがちです。それぞれの違いや特徴を知っておくと、自分やチームに合ったイベント形式を選べます。
発想イベントの違いを整理し、自社やチームでどれを使うかのヒントにしてください。
ハッカソンは、「ハック(hack)」と「マラソン(marathon)」を組み合わせた言葉です。エンジニアやデザイナーが中心となり、実際にアプリやサービスなどのプロトタイプを“短期間で開発”するイベントです。
たとえば、ハッカソンは「動くものを作る」のがゴールですが、アイデアソンは「新しい発想や企画案を量産する」ことに重点があります。ハッカソンはIT企業や開発系スタートアップで多く、エンジニアリングスキルが重要です。
一方、アイデアソンは職種や専門性を問わず、多様な参加者が価値を発揮できるイベントです。
ブレスト(ブレインストーミング)は、「自由に意見を出し合う会議の手法」です。アイデアソンやハッカソンと比べると、よりカジュアルで、短時間で実施できるのが特徴です。
たとえば、ブレストは日常の会議やミーティングで活用されますが、アイデアソンは「特別なイベント」として事前準備や審査も行われます。
「気軽なブレスト」か「本格的なアイデアソン」か、目的に応じて使い分けが必要です。
アイデアソン、ハッカソン、ブレストは、目的や場面で使い分けることが大切です。
たとえば、会社の新規プロジェクトや自治体の地域活性イベントなど「多様な人が集まる場」ではアイデアソンが効果的です。
エンジニア中心で「形にする」段階ならハッカソン、普段のチーム会議ならブレストが適しています。自社やチームの状況に合わせて、発想イベントをうまく使い分けてみましょう。

アイデアソンは新しい発想やつながりを生む強力なイベントですが、メリットだけでなくデメリットや注意点もあります。実際の運営や参加で「どんな良い点があるか」「どんな課題が起こるか」を事前に押さえておくと、より効果的なアイデアソンが実現できます。
良い点・注意点の両方をバランスよく理解しましょう。
アイデアソンには、大きく分けて3つのメリットがあります。
たとえば、普段接点のない異業種・異分野のメンバーが集まり、各自の経験や専門性をもとに新しい発想を生み出せます。
時間制限があるからこそ、思い切った意見や大胆な着想も歓迎され、普段の会議では出てこない斬新な案が次々に生まれることも多いです。イベントを通じて「協働力」や「相互理解」が深まり、新しいネットワークやコラボレーションも生まれやすくなります。
一方で、アイデアソンにはいくつかのデメリットや注意点もあります。
たとえば、アイデアを量産すること自体は簡単でも、「その後どう実現するか」が不明確だと“イベントで終わってしまう”ケースが多いです。進行役や運営がうまく全体を回せないと、参加者の意欲や発言量が偏り、盛り上がりに欠けることも。
初めて参加する人は「自分の意見が言いにくい」「どこまで自由に考えてよいか分からない」と感じる場合もあります。こうした課題を理解し、工夫や準備を重ねることで、成功率の高いアイデアソンを実現できます。

アイデアソンはさまざまな分野や現場で活用されています。目的やテーマによって運営方法も変わりますが、成功事例からは多くのヒントが得られます。
どんな場面で、どんな効果が出ているかを具体的に見ていきましょう。
企業の新規事業やサービス開発の現場では、アイデアソンが「新しい種」を生み出すきっかけとして定着しています。
たとえば、大手通信会社では数百人規模の社内アイデアソンから新規アプリやサービスが生まれ、プロジェクト化された事例もあります。
また、外部パートナーを招いた共同開催で、思いもよらない着想が実現し、既存事業の成長にもつながっています。
自治体や地域団体では、地元の課題解決やまちづくりのためにアイデアソンが活用されています。
たとえば、ある地方都市では「空き家対策」をテーマに市民・学生・企業でアイデアソンを開催し、実際にリノベーション事業が動き出したケースも。
行政だけでなく、多様な立場の人が「自分ごと」としてまちづくりに参画できるのが大きな魅力です。
学校や教育現場、NPO・コミュニティ活動でも、アイデアソンは学びや交流の手段として注目されています。
たとえば、大学では「産学連携アイデアソン」で企業からのリアルな課題を学生が解決。社会に役立つアイデアが生まれ、就職やキャリア形成にもつながっています。NPOや市民団体では、地域の悩みや新しい活動のアイデア出しを通じて、新しいプロジェクトが立ち上がることも多いです。
現場の課題解決からイノベーションまで、アイデアソンは幅広い分野で活躍しています。

アイデアソンはただ集まってアイデアを出すだけでなく、しっかりとした進め方や運営フローが大切です。テーマ選びから発表・フィードバックまで、スムーズに進めることで、成果と満足度が大きく変わります。
順を追って、基本の流れをわかりやすく解説します。
まず「どんなテーマでアイデアを出すか」を明確にします。
主催側は、テーマ選定とともに会場やオンラインツールの手配、当日の進行役(ファシリテーター)の準備をします。「ゴールや期待するアウトプット」を事前に全員に伝えることで、参加者もアイデアを出しやすくなります。
次に、参加者を公募または指名し、適切な人数・構成でチーム分けを行います。
「普段接点のないメンバー同士」のほうが斬新なアイデアが生まれやすいです。また、参加者の事前アンケートや簡単な自己紹介を取り入れると、チームビルディングが円滑に進みます。
アイデアソンの本番では、与えられたテーマについてチームごとに議論し、アイデアを出し合います。
進行役が「全員が発言できる雰囲気づくり」を大切にしながら、自由で活発なディスカッションを促します。
出されたアイデアの中から、特に実現性や新規性が高いものをチームで選び、発表用にまとめます。
短時間でも「発表の場」を設けることで、他チームとの刺激や意見交換が活発になります。
発表されたアイデアには、主催者やゲスト審査員、参加者全員からフィードバックや投票を行います。
ここで「良い点と改善点」「次につながるアドバイス」を伝えることで、イベント後の実現化や参加者の成長にもつながります。このように、ステップごとに丁寧な運営を心がけると、アイデアソンの成果が大きく高まります。

アイデアソンをより価値あるイベントにするためには、いくつかのポイントや工夫が大切です。初めて運営する場合や、もっと成果を上げたい場合は、ここで紹介するコツを意識して取り入れてみてください。
どんな現場でも役立つ“運営のコツ”をまとめます。
アイデアソン成功のカギは、主に次の3つです。
たとえば「どんな課題を解決したいのか」「どこまでの提案を求めるのか」を事前に共有するだけで、議論の質が大きく向上します。また、ファシリテーターが場を盛り上げたり、否定しない空気作りに徹することで、初参加の人でも安心して意見を出せます。
成果発表後は「次のステップ」や「実現に向けたサポート」を示すと、アイデアソンが“やりっぱなし”で終わりません。
進行役(ファシリテーター)は、アイデアソンの成否を左右する重要な存在です。
たとえば、話が止まったときは「他にこんな意見ありませんか?」と促したり、少数派の意見も丁寧に拾い上げると多様なアイデアが出やすくなります。「参加して良かった」と思える場作りが最も大切です。
最近はオンライン型アイデアソンも増えています。オンラインならではの注意点も知っておきましょう。
たとえば、ZoomやTeamsのブレイクアウト機能を使い、小グループでじっくり話す時間を設けると、アイデアが深まります。オンラインでも“参加者全員が発言できる工夫”が成功のカギになります。

アイデアソンは、単なるイベントにとどまらず、これからのビジネスや社会に大きな影響を与える仕組みとして注目されています。
企業や自治体、教育現場などでどんな可能性があるのかを見ていきましょう。
アイデアソンを通じて生まれるのは「単なるアイデア」だけではありません。
たとえば、複数部門のメンバーが垣根を越えて集まることで、それまで気づかなかった課題や新しい市場ニーズが見えてきます。また、イベントをきっかけに新規プロジェクトが立ち上がるケースも増えています。
最近は、日常業務やプロジェクト推進の中でも「ミニアイデアソン」を取り入れる企業が増えています。
たとえば、ある企業では「週次のミニアイデアソン」で現場課題を共有し、その場で具体的な改善案を決定・実行しています。このように、アイデアソンは“アイデアを生むだけ”でなく、“現場を動かす仕組み”にも進化しています。
これからは、企業・組織・地域社会のあらゆる場面で、アイデアソンの活用がさらに広がっていくでしょう。
アイデアソンは、多様な人が集まり短時間でアイデアを生み出す現代的な発想イベントです。ハッカソンやブレストとの違いを知り、メリット・デメリットや活用事例、進め方や運営のコツまで押さえれば、自分や組織でも活用しやすくなります。
アイデアソンの最大の価値は「多様な視点」と「自由な発想」にあります。
この3つを意識すれば、アイデアソンはただのイベントではなく、“新しい行動”や“現場の変化”を生み出す力になります。
もしあなたがこれからアイデアソンに参加したり運営したりするなら、まずは小さな規模でも実際にチャレンジしてみましょう。
新しい発想が求められる今だからこそ、アイデアソンの経験がきっと役立ちます。ぜひあなたの現場でも、アイデアソンを活かして新しい価値を生み出してください!
この記事を執筆した人

長尾 浩平
新規事業創出や事業戦略の専門家として、多様な業界での経験を持つコンサルタント兼起業家。
東京工業大学大学院 生命理工学研究科、および中国・清華大学大学院 化学工学科を卒業。グローバル企業において研究開発、新規事業企画、新市場参入戦略の立案、M&A支援、DXコンサルティング、営業戦略策定など、多岐にわたる業務を担当。業界を横断した豊富な経験を活かし、事業成長と競争力強化を支援する総合コンサルティングを提供。
2024年1月にVANES株式会社を創業し、企業の持続的成長を支援。変化の激しい市場環境において、戦略立案から実行支援まで一貫したアプローチで企業価値の最大化に貢献している。
人気記事
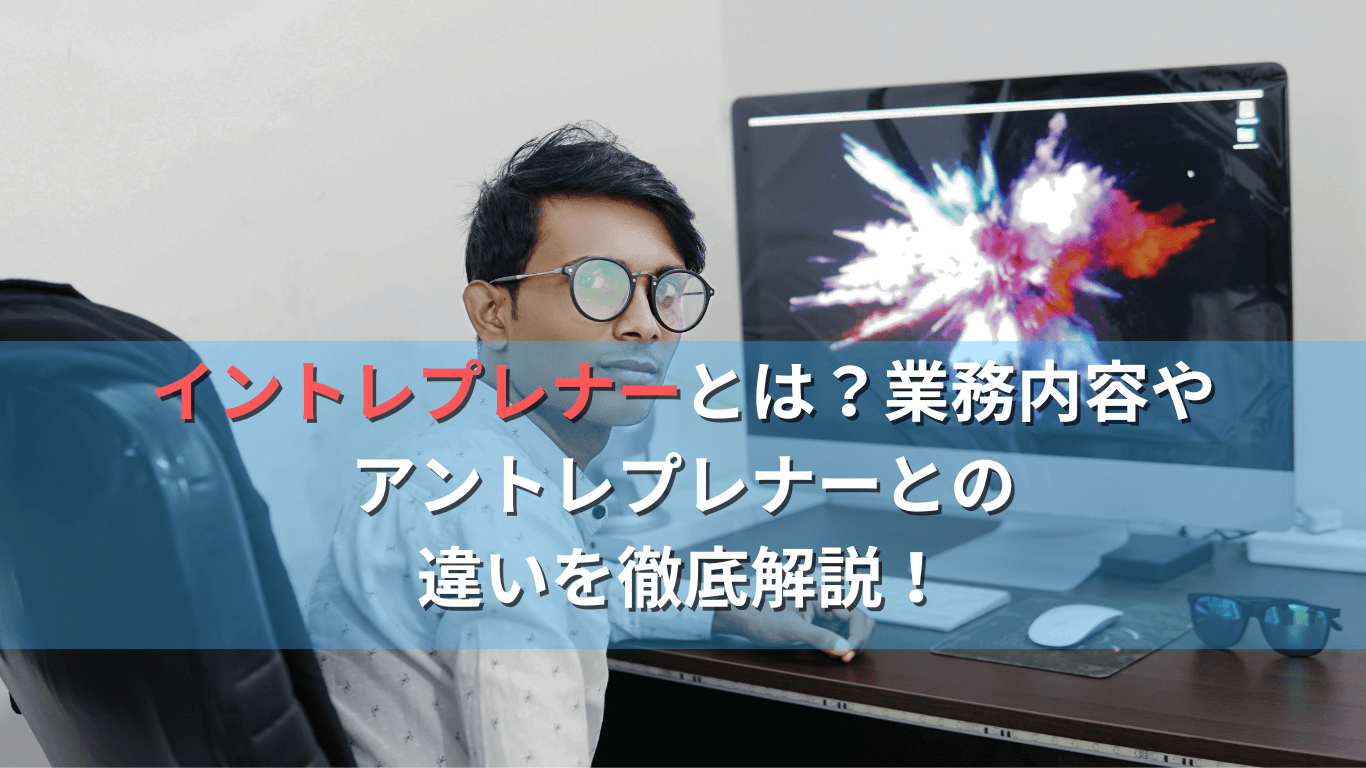
プロフェッショナルなビジネス用語集|2025.05.22
イントレプレナーって言葉、よく聞くけどどういう意味?アントレプレナーとは違うの? 「イントレプレナー」という言葉を最近よく耳にする...
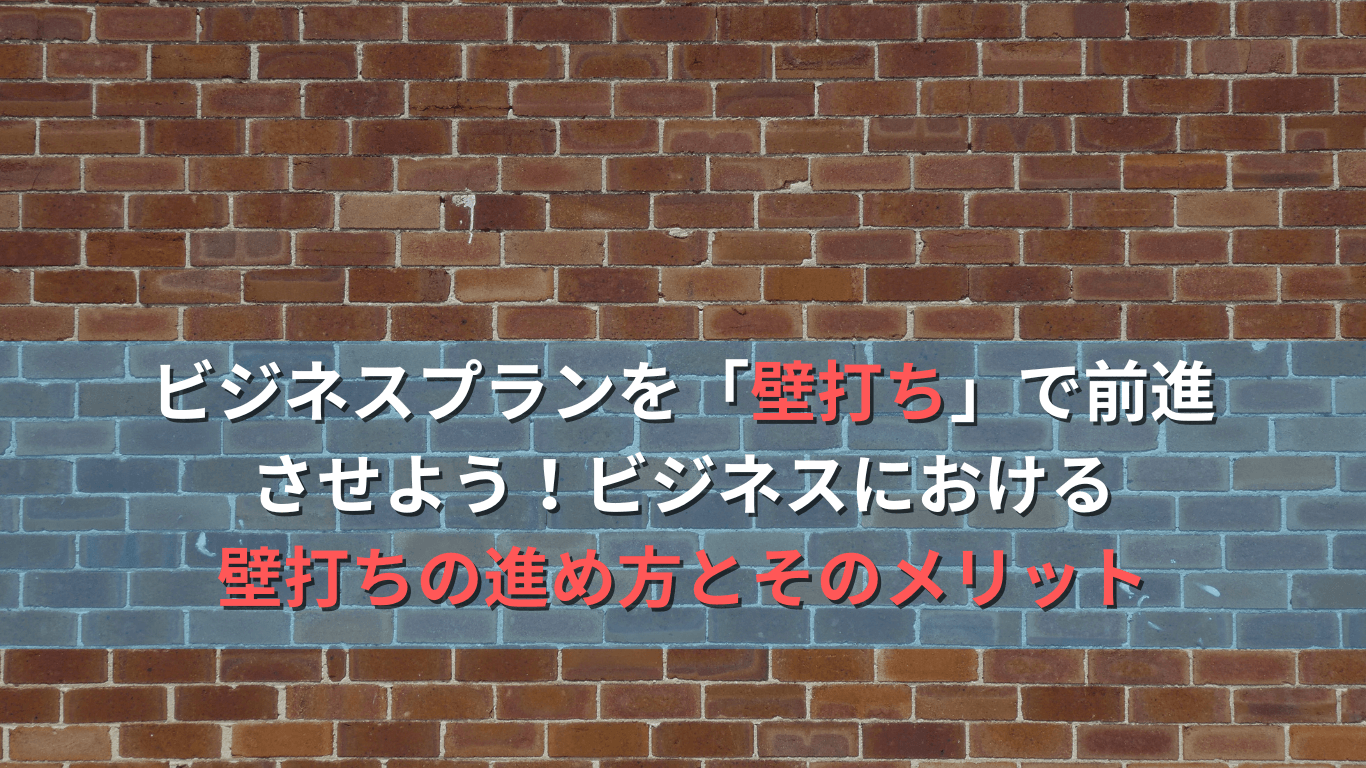
プロフェッショナルなビジネス用語集|2025.05.22
ビジネスでやる壁打ちってどうしたら効果があるの?ただの雑談になってしまいがち・・・ ビジネスにおける壁打ちとは、メンターなど様々な...

プロフェッショナルなビジネス用語集|2025.04.24
高度プロフェッショナル制度って自由に働ける仕組み? 裁量が増えるって魅力的だけど、長時間労働の不安もありますよね。 制度の中身を知...
カテゴリー