フリーコンサル独立準備ガイド|2025.05.22
【未経験からフリーコンサルになりたい方必見】初めて案件獲得までの完全ロードマップ
どうすれば独立できるの?なるには何から始める? やってみたい気持ちはあるけど、何を準備してどう始めればいいか不安になりますよね。 ...
Magazine

フリーコンサル独立準備ガイド
2025.05.27
フリーコンサルを始めて、このまま個人事業主でいるべきか、法人化に踏み切るべきか?法人化ってひとりしか社員がいなくてもできるの?
フリーコンサルとして高収入を得ても、節税対策をしなければ半分程度税金として徴収されます。節税効果や将来の収益を考えると、何も考えずに案件をこなすことに疑問を持ちますよね。法人化はタイミング次第で大きなメリットを得られることもあります。
そこで今回は、フリーコンサルが法人化するタイミングと、節税メリットを最大化する方法について紹介します!この記事を参考に、フリーコンサルとして高収入を得られている方は、法人化も検討してみてください。法人化をする方は、本記事のブックマークを推奨します。
この記事で分かること!
弊社サービスNewAceは、あなたのチャレンジを応援するコンサルタントの方向けのプラットフォームです。
案件のご紹介のほか、様々な相談も承っておりますので、是非下記よりご登録ください。

それでは、本章をチェックください。
目次

フリーコンサルタントとして働く場合、個人事業主となるため、税金に関する知識は欠かせません。この章では、フリーコンサルタントが知っておくべき税金の種類や仕組み、個人事業主として支払うべき税金について解説します。
税金の仕組みを正しく理解することで、無駄な支出を防ぎ、効率的に節税を行う準備が整います。
関連記事:未経験からフリーランスコンサルタントになるにはどうしたらいい?具体的な手順と準備の全知識を公開
フリーコンサルタントが支払うべき税金には、いくつかの種類があります。主な税金は以下の通りです。
例えば、所得税は確定申告時に収入から必要経費を差し引いた所得に応じて計算されます。また、フリーコンサルタントの多くは、収入が一定額を超えると消費税の課税事業者としての義務が発生します。
これらの税金を正確に把握し、計画的に支払うことが大切です。
所得税と住民税はフリーコンサルタントにとって特に重要な税金です。それぞれの仕組みを簡単に説明します。
例えば、所得税では課税所得が195万円以下の場合の税率は5%ですが、課税所得が330万円を超えると税率は10%に上がります。また、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、前年度の収入が多かった場合には高額になる可能性があります。
このような仕組みを理解しておくことで、無理のない納税計画を立てることが可能です。
フリーコンサルタントは個人事業主として、以下の税金も対象になります。
例えば、事業税はコンサルタント業が対象となるため、所得が一定以上の場合には必ず納付義務が生じます。また、自宅兼事務所の場合でも、固定資産税の一部が事業関連として計上される場合があります。
これらの税金を正しく理解し、計画的に対応することが重要です。

フリーコンサルタントとして働くうえで、税負担を軽くする方法を知ることは非常に重要です。この章では、具体的に実践できる節税方法を5つご紹介します。
これらの節税方法を活用することで、税負担を大幅に軽減することが可能です。
節税の基本は、必要経費を漏れなく正確に計上することです。経費として計上できる代表的な項目は以下の通りです。
例えば、仕事用のカバンや書籍も必要経費として計上できますが、私的利用が多い場合は経費として認められない場合があります。そのため、プライベートと仕事を明確に分け、領収書や明細書を保管しておくことが重要です。
青色申告を行うことで、最大65万円の所得控除が受けられる「青色申告特別控除」を活用できます。この控除を受けるための要件は以下の通りです。
例えば、会計ソフトを使うことで、複式簿記の管理が容易になり、手間を大幅に軽減できます。青色申告は、フリーコンサルだけでなくフリーランス全員に非常に大きな節税効果をもたらすため、積極的に利用することをおすすめします。
小規模企業共済は、個人事業主やフリーランスが利用できる退職金制度で、掛金が全額所得控除となります。主な特徴は以下の通りです。
例えば、月額3万円を掛けた場合、年間36万円が控除されるため、所得税と住民税を大幅に削減できます。老後の資金準備と節税を同時に実現できるため、フリーコンサルタントにとって非常に有益な制度です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人で加入できる年金制度で、掛金が全額所得控除となります。以下がiDeCoの主なメリットです。
例えば、月額2万円をiDeCoに拠出すると、年間24万円が控除されるため、所得税と住民税の負担が軽くなります。さらに、将来の老後資金として積み立てができるため、一石二鳥の効果があります。
事務所で使用する設備や機器を購入するのではなく、リースを活用することで節税が可能です。リースのメリットを以下に挙げます。
例えば、パソコンやプリンターなどの高額な機器をリースで導入することで、購入時の負担を軽減しつつ、毎月の経費として計上できます。初期費用を抑えながら、節税効果を得られる点で非常に優れた方法です。

今までの話は、個人事業主としてフリーコンサルタントの活動をしていく場合の話です。売上が伸びてきたら、個人事業主よりも法人の方が税制面を見てもメリットが大きいです。フリーコンサルタントが法人化を検討する際、タイミングの見極めが成功の鍵を握ります。
では、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
法人化を考える上で、まず注目すべきは「年収」です。フリーコンサルの売上が800万円以上の場合、法人化による節税効果が高くなる傾向があります。
個人事業主だと、累進課税で売上が大きくなるにつれて税率が上がり、利益額が4,000万円以上になると45%が税金で引かれるのに対して、法人化すると利益が800万円以上からは23.2%の税率となります。具体的に法人化を検討する基準としては以下が挙げられます。
例えば、フリーコンサルとして年収1,200万円を超える方の場合、法人化を行うことで所得税率が抑えられ、さらに経費として家賃や通信費を計上できるため、300万円以上節税できる可能性があります。
結論として、売上が一定額以上になった場合は法人化を前向きに検討するべきです。
法人化のタイミングを判断する際には、次の3つのポイントを確認しましょう。
これらのポイントを踏まえ、将来的なビジョンを考慮して法人化の決断をすることが重要です。
法人化をスムーズに進めるためには、事前準備が欠かせません。以下の3つのステップを実行しましょう。
会社の設立だけであれば、特に障壁なく進められると思います。
また、フリーコンサル以外の事業を実施していく場合は、事前準備を怠らないことで、法人化後の運営もスムーズになります。

法人化を行うことで、フリーコンサルタントが得られる節税メリットは非常に大きいです。所得税や法人税の違いを活用し、経費を最大限に活かすことで、税金の負担を軽減できます。
これらのポイントを理解することで、節税効果を最大化する方法が見えてきます。
個人事業主としての所得税は累進課税であるため、所得が増えるほど税率も高くなります。一方で、法人化を行うと、法人税は一定の税率(中小企業では15~23.2%)が適用されるため、所得が高いほど節税効果が大きくなります。
具体的に、年収1,200万円の個人事業主が法人化した場合、年間で300万円以上の税金が軽減される可能性があります。節税効果を得るためのポイントは以下の通りです。
法人化すると、役員報酬を設定することで所得を分散できるようになります。役員報酬は給与として経費扱いになるため、法人税を圧縮できるのが大きな利点です。例えば、年収1,200万円をそのまま個人所得とする場合、所得税率は20%前後になります。
しかし、法人化して役員報酬を分散すると以下のメリットが得られます。
家族がいる経営者は、役員報酬を夫婦で分けることで年間100万円以上の節税に成功できる可能性があります。役員報酬の活用は法人化後の大きな強みとなります。
法人化すると、経費として認められる支出の範囲が拡大します。個人事業主では経費計上が難しいものも、法人化によって認められるケースがあります。
具体的には以下の支出が挙げられます。
例えば、自宅を法人契約に切り替え、社宅とすることで賃料を法人負担とすることで、毎月の家賃負担を大幅に軽減することが可能です。このように、経費の幅を広げることで現金の流出を最小限に抑えることができます。
個人事業主の場合、所得税は累進課税で最大45%となりますが、法人税は15%~23.2%の範囲内に収まります。また、法人化すると住民税や事業税も減額される可能性があります。
以下は法人税と個人税率の比較です。
この違いにより、特に年収が高いフリーランスほど法人化の節税効果が大きくなります。例えば、年収1,500万円のフリーコンサルタントは、法人化を通じて年間300万円以上の税金を節約できるようになりました。
節税メリットを最大化するためには、以下のステップを実行するのが効果的です。
例えば、ある方は税理士と相談し、役員報酬を月々分散し、さらに福利厚生費として社員向けのサービスを導入。その結果、税負担が年間で30%軽減され、資金を事業拡大に活用できるようになりました。

法人化には、多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。フリーコンサルタントが自分の状況に合った選択をするためには、両者を比較し、バランスよく判断することが重要です。
これらの情報を基に、自身にとって最適な選択を見つけていきましょう。
法人化することで得られる代表的なメリットは以下の5つです。
例えば、法人化したフリーコンサルS.Aさんは、大手企業との取引条件が法人化後に大幅に改善され、プロジェクト単価が20%上がったという事例があります。
一方で、法人化には以下のデメリットも存在します。
設立後の事務作業の多さに困った方もいます。税理士に業務委託することで解決しましたが、その費用もかかるため、当初の想定よりも費用がかかってしまったそうです。
法人化を決断する際は、以下の基準でメリットとデメリットを比較しましょう。
例えば、年収900万円のJ.Tさんは、法人化により節税効果を得つつ、将来的な社員雇用を視野に入れた長期計画を実現しています。
結論として、法人化は短期的な節税だけでなく、事業の成長と安定性を見据えて判断することが重要です。

法人化を成功させるためには、事前準備や計画が非常に重要です。特に、専門家のサポートを受けながら、必要な手続きや管理をスムーズに進めることが鍵となります。
これらのポイントを押さえることで、法人化を円滑に進めることが可能です。
法人化を検討する際は、税理士や司法書士などの専門家に相談も大切です。専門家は、以下の分野で重要なアドバイスを提供してくれます。
例えば、税理士に相談したフリーコンサルK.Tさんは、法人化前に役員報酬をシミュレーションし、最適な設定で税金を20%削減できました。専門家の力を借りることで、リスクを最小限に抑えつつ、スムーズな法人化を実現できます。
法人設立のプロセスは、次のようなステップで進みます。このプロセスを理解したうえで、自分が時間を捻出できるかどうかと照らして実施してみてください。
法人化後は、日々の管理や維持が事業の成功に直結します。以下のポイントに注意して、運営を安定させましょう。
法人運営にはコストや手間がかかる一方で、適切に管理することで信頼性や効率が向上します。これらのポイントを実践することで、フリーコンサルタントとしての法人化を成功に導くことが可能です。
フリーコンサルタントとしての次のステップを見据え、ぜひ法人化を前向きに検討してみてください。

法人化を成功させるだけでなく、法人化後に事業を拡大し、持続的な成功を目指すことが重要です。特に、経営戦略や収益拡大のプランを明確にし、実行に移すことで、法人化の効果を最大限に引き出すことができます。
これらの内容を参考にして、法人化後の経営を軌道に乗せましょう。
法人化後は、事業拡大を視野に入れた明確な戦略設計が欠かせません。以下のステップで事業戦略を構築しましょう。
戦略を明確に持つことで、計画的な成長が可能になります。
また、起業の準備資金を得るためにフリーコンサルタントになられた方は、下記記事も参考にしてみてください。
法人化後の安定した収益基盤を作るには、リピート顧客を増やす施策が必要です。以下の方法を活用して、既存顧客との関係を深めましょう。
リピート顧客を増やすことで、事業の安定性が大幅に向上します。
関連記事:フリーコンサル必見!案件継続のためのクライアントとの信頼構築術とコツ
新規顧客を獲得するには、効果的なマーケティング戦略が必要です。以下の方法で新しいクライアントとの接点を増やしましょう。
新規顧客獲得のための施策を積極的に展開することが、事業成長のカギです。
フリーコンサルタントになりたいけど税金面のことが不安、フリーコンサルタントとして活動しているけど税金を多く払っている気がする。そんな方に向けて、弊社NewAceに登録いただけたら、フリーコンサルタント経験者が担当者として相談に乗ることも可能です。
面談時に、フリーコンサルタントとして活動していく上で不安なことがあれば、気兼ねなくお申し付けください。

最後に、会社法人を設立するまでの流れを解説します。法人を設立するには、正しい順番で手続きを進めることが大切です。流れを把握していないと、無駄な手間や費用がかかってしまいます。これから法人化を考えているフリーコンサルの方に向けて、必要なステップを3つに分けて解説していきます。
この順に進めることで、法人化の手続きをスムーズに完了できます。
法人化で最も重要なのは、最初に「どんな会社にするか」を明確にすることです。最初の段階で曖昧なままだと、後から変更が必要になり、手続きが複雑になります。特に会社形態、資本金、決算期の決定は慎重に行いましょう。
以下のような項目を事前に決めておく必要があります。
中でも「株式会社と合同会社のどちらを選ぶか」は、多くのフリーコンサルが悩むポイントです。
| 株式会社が向いている場合 | 合同会社が向いている場合 |
| ・社会的な信用を重視したい ・融資や資金調達を見据えている ・株式の売買や事業承継を想定している | ・設立費用や維持コストを抑えたい ・少人数でシンプルに経営したい ・外部からの信用をさほど必要としない |
また、資本金は1円から設立可能ですが、実務では50万円〜100万円が現実的です。銀行口座の開設や取引先の信頼にも影響します。役員報酬を設定しないことも可能ですが、社会保険の加入条件や節税に影響が出るため、慎重に検討する必要があります。
ここまでが会社設立の「土台作り」です。次は、実際に会社を形にする「定款作成と資本金払い込み」に進みましょう。
基本情報が決まったら、次は会社のルールを文書にまとめる「定款」を作成します。定款は会社の憲法のようなもので、設立後のトラブル防止にもつながります。特に事業目的や株式に関する内容は正確に書くことが大事です。合同会社の場合は定款の認証が不要なので、手続きが1つ少なくなります。
定款を作るときは、以下の内容を盛り込みます。
定款認証の例:株式会社を作る場合
定款が完成したら、次は資本金の払い込みです。会社設立前に、代表者個人の口座に資本金を振り込みます。通帳に振込名義や日付が明確に記録されていることが大切です。
資本金の払い込みは、登記の前に行う必要があります。忘れると設立ができないので注意が必要です。定款と資本金がそろったら、いよいよ法務局へ「登記申請」に進みます。7登記後は届け出や口座開設を忘れずに
法務局で登記申請を行えば、晴れて法人が設立されたことになります。
登記申請が完了してもまだ終わりではありません。設立後すぐに行うべき手続きがいくつかあります。これらを怠ると、税金や取引に支障が出ることもあります。法人設立後にやるべきことは、以下の通りです。
まずは、法務局で登記が完了したら「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」と「印鑑証明書」を取得します。これらは銀行口座の開設や届出で必須になります。次に、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場へ次の届出を行います。
また、法人名義の銀行口座を開設しますが、審査があるため、時間がかかる場合があります。スムーズに進めたい場合は、あらかじめ必要書類をそろえておきましょう。
法人用のクレジットカードは、事業用の支出管理や経費計上に便利です。会計ソフトも個人事業用から法人向けに切り替えることで、仕訳や税務処理がスムーズになります。
最後に、顧問税理士の契約を検討しましょう。設立初年度は税務処理が複雑になりやすいため、最初から信頼できる専門家と組むのが安心です。
ここまでのステップを確実にこなすことで、法人設立後のトラブルや手戻りを防げます。焦らず一つずつ進めていきましょう。

法人化を検討する際、多くの方が疑問や不安を抱えます。ここでは、フリーコンサルタントが抱きやすい質問に対して、具体的な回答を示します。
これらの疑問を解消し、自信を持って法人化を進めていきましょう。
法人化にかかる初期費用は、主に以下の項目から構成されます。
全体で約20〜40万円程度が目安ですが、自分で手続きを行うことで費用を抑えることも可能です。特に、電子定款を利用することで紙の定款よりも4万円程度安くなるためオススメです。
法人化による節税効果は、個人事業主の収入や経費の状況によって異なります。以下は、法人化による節税の目安です。
例えば、年収1,200万円のフリーコンサルタントが法人化を行い、家賃や通信費を経費計上した場合、年間40万円以上の節税を実現したケースがあります。節税効果を最大化するには、税理士と相談し、収益や支出に応じた最適なプランを立てることが重要です。
法人化に向いている人には、以下のような特徴があります。
例えば、企業向けにコンサルティングを提供するフリーコンサルの方で、取引先から法人化を求められるケースが増えたため、法人化を決断された方もいます。その結果、大規模な案件を受注できるようになり、売上が1.2倍に増加しました。
法人化後、社会保険の加入が義務化されるため、社会保険料が発生します。これは、法人化後の最大のコスト増の一つと言えます。以下のポイントに注意してください。
法人化後に役員報酬を年額400万円に設定した方は、社会保険料が月額6万円程度となり、想定内のコストで運営を開始できます。
税理士や社労士に相談し、事前に負担額をシミュレーションしておくことをおすすめします。
すべてのフリーランスが法人化すべきというわけではありません。以下の状況に該当する場合は、個人事業主のままでいるほうが良い場合もあります。
まだ事業を始めたばかりだと、売上が安定していないため法人化を見送り、個人事業主として事業を軌道に乗せてから法人化を再検討した方がいい場合もあります。自分の事業規模や将来計画に合わせて、慎重に判断することが大切です。

フリーコンサルタントが法人化を検討する際、タイミングや準備、そして法人化後の戦略が非常に重要です。この記事では、法人化に関する基本情報から具体的なメリット・デメリット、そして成功するための具体策まで詳しく解説しました。
これらを押さえることで、法人化を事業の成長につなげることができます。この記事が、法人化を検討するあなたにとって有益な情報となり、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
これからもあなたのビジネスの成功を心より応援しています!
コンサル案件をお探しならフリーコンサルマッチングサービス|Re-neWにぜひご相談ください。
この記事を執筆した人

長尾 浩平
新規事業創出や事業戦略の専門家として、多様な業界での経験を持つコンサルタント兼起業家。
東京工業大学大学院 生命理工学研究科、および中国・清華大学大学院 化学工学科を卒業。グローバル企業において研究開発、新規事業企画、新市場参入戦略の立案、M&A支援、DXコンサルティング、営業戦略策定など、多岐にわたる業務を担当。業界を横断した豊富な経験を活かし、事業成長と競争力強化を支援する総合コンサルティングを提供。
2024年1月にVANES株式会社を創業し、企業の持続的成長を支援。変化の激しい市場環境において、戦略立案から実行支援まで一貫したアプローチで企業価値の最大化に貢献している。
人気記事
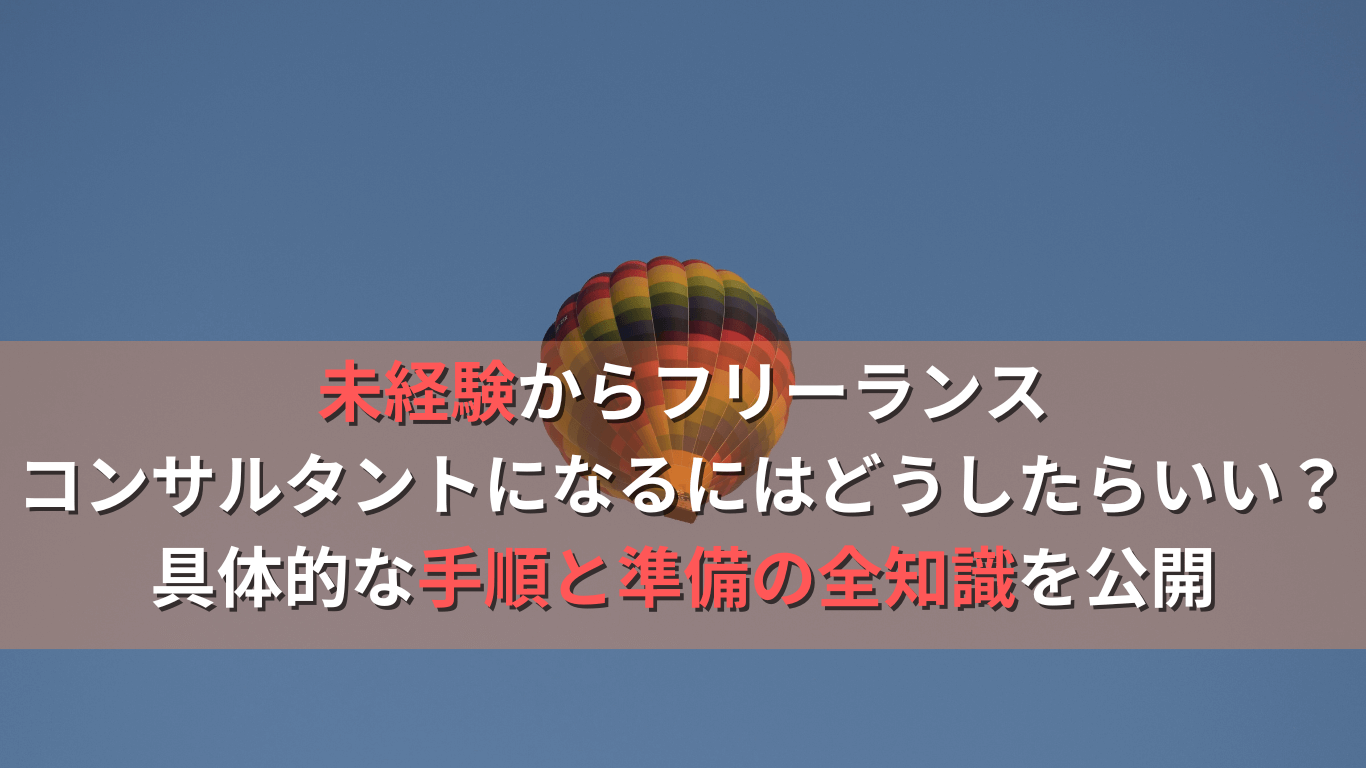
フリーコンサル独立準備ガイド|2025.05.22
どうすれば独立できるの?なるには何から始める? やってみたい気持ちはあるけど、何を準備してどう始めればいいか不安になりますよね。 ...
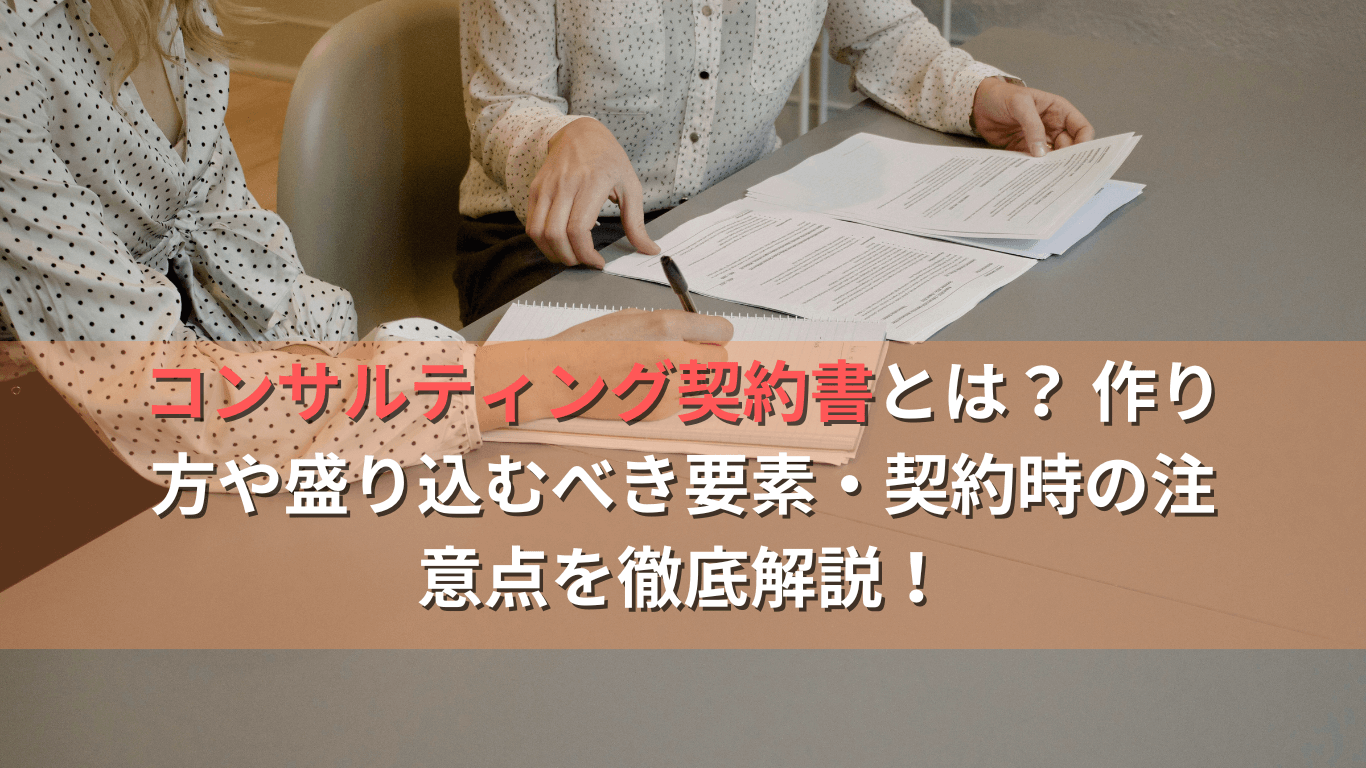
フリーコンサル独立準備ガイド|2025.05.22
フリーコンサルで案件に参画する際、契約書にサインしたけど、そもそもコンサルティング契約書ってどんな書類?あまり読まずにサインしたけ...

フリーコンサル独立準備ガイド|2025.01.09
「業務委託契約ってどう働くの?」フリーコンサルとして働くなら、業務委託契約の選択肢が気になるところ。メリットが多い一方で、契約内容...
カテゴリー