プロフェッショナル人材をお探しなら|2025.07.02
【チームビルディング】リーダー向け完全ガイド!すぐ使える施策例10選と注意点もご紹介
チームビルディングって何?チームをまとめたいけれど、何をどう始めればいいの? リーダーになってチームをまとめる必要が出てきたけど、...
Magazine

プロフェッショナル人材をお探しなら
2025.05.22
オープンクローズ戦略って、実際どう使うの?
任天堂やAppleがうまく使っているって聞いたけど…
自社のサービスについて、何をオープンにしてどこを守るか、その選択も企業の戦略のひとつです。
曖昧な理解では、自社で開発した成果を他社に取られて、自社サービスが破綻するかもしれません。
今回はオープンクローズ戦略の基本から応用、導入時の注意点まで紹介します!
自社戦略としてオープンクローズ戦略を採用している方、コンサルタントとしてこの戦略をフレームとして提案しようとしている方に、ヒントを提供する記事となっています。
弊社サービスNewAceは、あなたのチャレンジを応援するコンサルタントの方向けのプラットフォームです。
案件のご紹介のほか、様々な相談も承っておりますので、是非下記よりご登録ください。

それでは、本章をチェックください。
目次

オープンクローズ戦略とは、会社の持つ技術やノウハウの「見せる部分」と「見せない部分」をうまく分けて使う戦略です。
技術の一部だけを外に公開し、本当に大事な部分や自社の強みになる秘密は外には出しません。
こうすることで、外部と連携して新しい市場や価値を生み出しながら、コア技術や利益の源泉は自社に残し、成長と競争力を両立できます。
大企業だけでなく、中小企業やスタートアップにも有効な戦略です。
詳細を解説する前に、オープンクローズ戦略の代表的な型を紹介します。
オープンクローズ戦略は、「どこを開放し、どこを守るか」という設計によって、その形が大きく変わります。
ここでは、多くの企業が実際に採用している4つの代表的なパターンを解説します。
AppleのiPhoneを例にすると分かりやすいでしょう。iOSという根幹部分やハードウェア設計は自社内で厳密に管理していますが、アプリ開発キットやApp Storeの仕組みは世界中の開発者に開放しています。
これによってiPhone上で動くアプリの多様性が生まれ、ユーザーの選択肢が広がり、結果的にApple自身も大きな利益を得るというエコシステムが成立しています。
「自分たちだけの独自技術」と「みんなに使ってもらう仕組み」を両立させる戦略です。
コカ・コーラのレシピは長年、世界中で厳重に守られてきました。いくら他社が努力しても、本物の味は再現できないと言われています。
完全クローズ型の戦略では、競争力の核となる部分を外部に一切出さず、情報の漏洩や模倣のリスクを最小限に抑えます。
その代わり、周辺ビジネスや連携の幅は限定されてしまうことも多いです。
USBやBluetoothは、技術仕様を世界中に公開し、どのメーカーでも使えるようにしています。
これにより一気に普及が進み、世界標準のプラットフォームとなりました。競合も多くなりますが、標準を握ることで業界全体をリードする立場を確立しています。
「自社グループや特定パートナーにだけ技術を開放する」「用途や地域を限定してオープンにする」といった、“条件付きのオープン”です。
例えば大手家電メーカーが、自社グループのサプライヤーには部品技術を共有するが、競合他社には公開しないといった例がこれに当たります。
広げすぎず、でも囲い込みすぎない──両者のバランスを取るやり方です。
実際には、企業ごと・タイミングごとにこの4つを組み合わせて、より柔軟なオープンクローズ戦略が展開されています。
実際にオープンクローズ戦略を立案・実行する際は、次のステップを踏むことが一般的です。
では、オープンクローズ戦略を自社で活用するために、詳細を見ていきましょう。

オープン戦略とは、自社の技術や仕様をあえて外部に公開する戦略です。他社やユーザーとの連携を通じて、市場の拡大や共創を狙います。
オープン戦略の鍵は、「普及」と「共創」の加速です。
たとえば、Googleが提供するAndroidは代表例です。Android OSは、基本ソースコードをオープンにしています。
その結果、世界中のメーカーが参入し、普及率が圧倒的になりました。他にも、オープンなAPIやSDKを公開することで、周囲の企業が製品やサービスを展開できます。
オープン戦略の実行で得られるメリットとデメリットは以下の通りです。

実際、Androidは世界に普及しましたが、Google以外のメーカーにも恩恵が分散されました。つまり、「普及はするが、儲かりにくい」という構図になりがちです。
あなたの会社でもオープン戦略を使う場面はあるでしょう。ただし、コアの利益をどこで出すのかを考えずに進めると、思ったほど収益が上がらない可能性もあります。
このように、オープン戦略にはチャンスもありますが、リスクもあるのです。
クローズ戦略とは、自社の技術やノウハウを外部に公開しない戦略です。競合他社から模倣されないよう、情報を囲い込むことが目的です。
クローズ戦略の要点は「差別化」と「独占」です。
たとえば、コカ・コーラのレシピは完全非公開です。また、Dysonのモーター技術も徹底的に秘匿されています。これにより、高価格帯でもブランド価値を維持できています。
クローズ戦略の実行で得られるメリットとデメリットは以下の通りです。

クローズ戦略だけでは、イノベーションや共創が進みにくい側面もあります。
つまり、守りには強いが、拡がりにくいのがクローズ戦略の特徴です。そのため、オープン戦略とのバランスが重要になってきます。
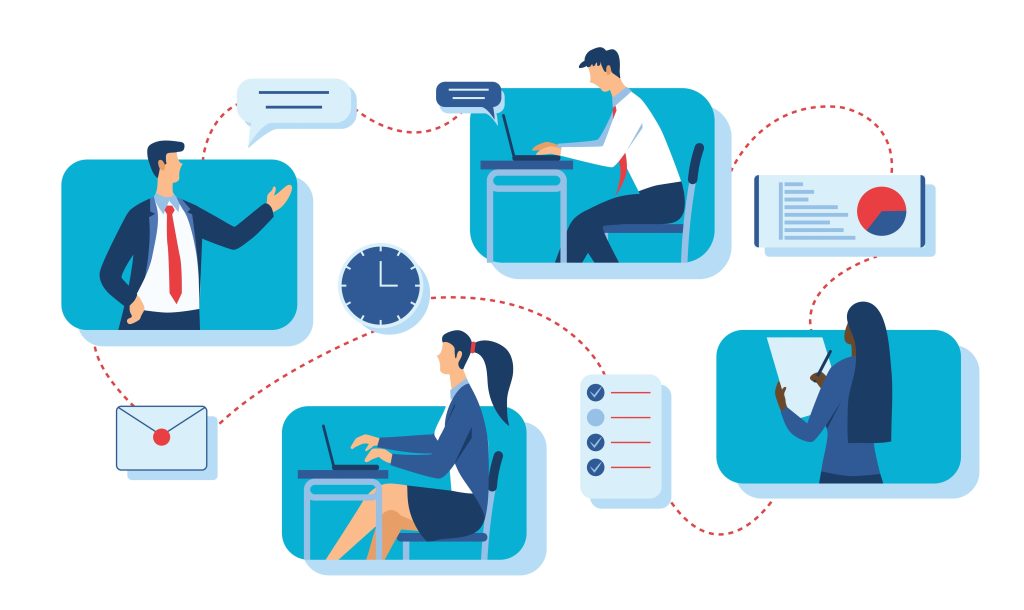
オープンクローズ戦略を成功させるには、事前の設計がカギです。特に、どこを開き、どこを閉じるかの判断が重要です。
最初にやるべきは、自社の「コア技術」の特定です。
オープンクローズ戦略では、コア技術を軸に全体設計を進めます。
そのためには、まず「何が自社の強みか」を言語化する必要があります。
コア技術の特定には、以下の観点が有効です。
たとえば、AIスタートアップなら学習済みモデルの設計手法やデータ収集ノウハウが該当します。
メーカーなら、高精度の加工技術や材料技術が中心になるでしょう。
技術の再現性が低い、ユーザー満足度に直結する、社内にしかない知見やノウハウ、保護手段が存在する(特許、商標など)など、実際の企業でも、コア技術を軸に設計しています。
Appleは、OSとアプリの密接な連携をコアとし、外部には限定的に開放しています。
一方、周辺機器やAPIはある程度公開し、開発者を巻き込んでいます。
つまり、「何を武器にするか」を見極めることが、すべての出発点なのです。
コア技術の明確化ができれば、次に進むべきは「どこまでをオープンにするか」の判断です。
コア技術が見えたら、次は公開・非公開の線引きが必要です。
「どこまで開くか」「どこを守るか」の選定が成否を分けます。
この判断で意識すべきは、「自社が得るべき価値は何か」です。
たとえば、プラットフォームビジネスでは中核技術を囲い、周辺を開放するケースが多いです。
このバランス設計が、まさにオープンクローズ戦略の真髄です。「何を渡し、何を守るか」の見極めが企業の命運を左右します。
オープンクローズ戦略と知財戦略は切っても切れません。特に特許や商標などの知財は、クローズ領域を守るための武器です。
知財をどう活用するかが、戦略の実行力を決めます。
技術やノウハウを外部にどう扱わせるかは、「秘匿」「特許」「ライセンス」などの手段を使い分けることで実現します。
自社技術の価値や事業戦略、パートナーとの関係性によって、最適な出口戦略を選択する必要があります。
ライセンスには「独占」と「非独占」という大きな違いがあります。
例えば、半導体IPのビジネスでは、戦略的パートナーには独占ライセンスを提供し、広く普及を狙う分野では非独占ライセンスを活用することが多いです。
たとえば、ライセンス戦略を設計することで、オープンにしても利益を確保できます。Appleは特許で囲い込みながら、外部との連携で製品力を高めています。

知財は「盾」にも「刃」にもなるので、効果的に使うためには、法務と現場が連携したマネジメント体制が不可欠です。
オープンクローズ戦略は「切り分け」だけでは不十分です。
オープン領域とクローズ領域が有機的につながってこそ、真の効果が生まれます。
単に技術を分けるだけでは、市場での支配力は築けません。
たとえば、AppleはApp Storeを開放していますが、決済は全て自社で管理しています。
このように、外部の力を使って、内部の価値を最大化する構造が大切です。
この構造設計が甘いと、普及しても収益が取れない状態になります。
つまり、オープンクローズ戦略の本質は「設計の巧妙さ」にあります。
単なる切り分けではなく、全体最適なシステムを設計しましょう。

オープンクローズ戦略は、技術の「開放」と「囲い込み」を両立させる戦略です。そのため、適切に設計すれば、普及と利益の両方を手に入れることができます。
このような両立ができる点が、最大の強みです。ここからは、具体的なメリットと、実行時に注意すべきポイントを見ていきます。
オープンクローズ戦略が注目される最大の理由は「矛盾の打破」です。普通は「普及」と「高収益」はトレードオフになります。
オープンにすれば拡がるが、儲からない
クローズにすれば儲かるが、拡がらない
しかし、この2つを同時に実現できるのがオープンクローズ戦略です。
たとえば、任天堂のSwitchは一部仕様を開放し、ゲーム開発者を巻き込みました。一方で、プラットフォームや製造技術は厳重に囲い込んでいます。
結果として、ゲームも普及し、本体も売れ、利益も取れたのです。
このような設計により、企業は「拡がるのに儲かる」状態を作れます。それが、従来の戦略との圧倒的な違いです。
一方で、オープンクローズ戦略には実行リスクもあります。
「線引きの甘さ」が、全てを崩壊させる要因になります。
どこまで開くか、どこまで守るかの判断がブレると、以下のような問題が起きます。
たとえば、APIを無制限に開放してしまい、競合企業が模倣するケースは多いです。また、ライセンスの設計が甘く、外部が収益を独占してしまう例もあります。
さらに、オープンとクローズを切り分ける内部体制が整っていないと、混乱を招きます。
つまり、「戦略として設計できていないと機能しない」のです。
この戦略は、設計、運用、管理すべてが揃って初めて効果を発揮します。
実行の際には、事業責任者・知財部門・技術部門が一体となって動く必要があります。
「切り分けたら終わり」ではなく、「設計し続ける覚悟」が重要です。

ここからは、実際の企業がどのようにオープンクローズ戦略を活用しているのかを紹介します。
成功企業の戦略を知ることで、自社導入のヒントを得ることができます。
それぞれの事例から、設計・運用・収益化の視点で学びましょう。
Appleは、オープンクローズ戦略の代表的成功企業です。製品設計、OS、サービス、すべてに戦略が貫かれています。
Appleの本質は、「囲い込みつつ、巻き込む構造設計」です。
たとえば、iPhoneは自社設計のiOSでしか動きません。しかし、App Storeを開放し、世界中の開発者を取り込んでいます。
開発者は自由にアプリを作れますが、販売や決済はAppleが管理しています。
結果として、iPhoneは世界中で普及しつつ、高収益体制を築いています。このバランス感覚が、Appleの競争優位の源泉です。
あなたの会社でも、「開放と囲い込みの導線」を設計すれば、Appleのように普及と利益を両立できる可能性があります。
任天堂は、オープンクローズ戦略を巧みに活用することで、家庭用ゲーム市場で圧倒的なブランド力と長期的な成長を実現してきた企業の代表例です。
同社は、まずゲーム機本体やOS、独自のコントローラーなど、コアとなる技術やユーザー体験の“核”となる部分を徹底的に自社管理しています。
たとえば、Nintendo Switchのハードウェア仕様や通信システムは、外部には簡単に明かしません。
これによって、模倣や安易な参入から自社の競争力を守っています。
一方で、ゲームソフトの開発環境やプラットフォーム(いわゆるSDKやライブラリ)、さらにはSwitch Onlineのサービス基盤などは、外部の有力なゲーム会社やクリエイターに積極的に開放しています。
任天堂公式のパートナープログラムや開発支援体制を通じて、外部のソフトメーカーが自由に魅力的なゲームタイトルを開発できるようにし、その多様なソフト群がユーザーの支持を集めています。
この「囲い込み」と「開放」の使い分けによって、任天堂は自社ブランドの独自性を守りながらも、多くのパートナー企業や開発者を巻き込み、ゲーム市場そのものを拡大してきました。
とくに「任天堂のゲーム機でしか遊べない」魅力と、「多彩なゲームタイトルが集まる」開放性を両立させることで、ファン層を拡大し続けています。
三菱電機も、オープンクローズ戦略を産業分野で巧みに使っています。
特に注目すべきは、FA(ファクトリーオートメーション)領域での戦略です。
たとえば、MELSECシリーズは通信仕様の一部を公開しています。その一方で、制御アルゴリズムやソフトウェアは非公開です。
この戦略により、産業分野での標準化と自社製品の優位性を両立しています。
つまり、「外とつながりつつ、中は強くする」設計です。
あなたの業界でも、似た構造を設計することで市場の主導権を握れるかもしれません。
知財の活用は、オープンクローズ戦略の実行を支える土台です。
特に、技術やブランドを守るだけでなく、利益を生み出す源泉にもなります。
以下に、実際の企業による知財活用の具体事例を紹介します。
IBMは、年間数千件の特許を保有し、そのライセンス収入だけで数千億円規模の利益を出しています。この仕組みは、技術をクローズ領域でしっかり守りつつ、ライセンスという形でオープンな収益源に変換している例です。
また、トヨタは燃料電池関連の技術の一部を公開しました。だれでも使えるように見せつつ、最重要の生産技術や部材技術は秘匿しています。
これにより、業界全体を巻き込んで市場を拡大しつつ、供給やブランドで優位性を保っています。「開放しても主導権を失わない」という設計がポイントです。
オープンクローズ戦略では、知財の位置づけが重要です。
守るべきもの、開放すべきものを知財視点で整理すれば、より堅牢な戦略が築けます。
弊社NewAceでも、過去オープンクローズ戦略に関する案件について携わったこともあります。
オープンクローズ戦略戦略を自社に導入されたい企業様は、こちらから弊社宛にご連絡ください。選任のプロフェッショナルがご対応いたします。
また、こうした戦略案件をお探しのプロ人材の方も是非弊社までご連絡ください。


オープンクローズ戦略は強力な武器である一方、運用を誤ると競争力低下や情報流出のリスクを招くこともあります。
成功のためには、守るべき領域の見極めや社内体制、契約管理など、慎重な対応が欠かせません。ここでは、実践時に注意すべきポイントを解説します。
オープンクローズ戦略を実行するうえで、最も注意すべきなのが「技術流出」と「競争力の低下」です。技術やノウハウを安易に開放しすぎてしまうと、模倣やコピー製品の拡大につながり、価格競争や利益率の低下を招く恐れがあります。
一方で、逆にすべてを囲い込もうとすると、市場そのものが拡大せず、せっかくのパートナーシップや新規ビジネスの機会を逃してしまいます。
この両者のバランスを見極めることこそが、経営層や戦略担当者に求められる最大の課題です。
「どこまで開放し、何を守るべきか」は、常に市場環境や技術動向、競合の状況を踏まえて再検討していく必要があります。
戦略を形だけで終わらせないためには、実際に動かすための社内体制が不可欠です。
法務や知財部門、そして現場の技術担当者や営業部門が一体となり、情報共有や役割分担を明確にすることで、戦略が現場で適切に機能します。
パートナーとの契約では、特許ライセンスや共同開発契約、秘密保持契約など、多様な知財スキームを活用しつつ、将来的な技術応用や利用範囲についても柔軟な見直しが可能な体制づくりが重要です。
市場や技術が変化する中で、契約内容をタイムリーにアップデートできるような仕組みを作ることで、長期的な競争力を維持できます。
オープンクローズ戦略を持続的に機能させるためには、社内外の「ガバナンス設計」が鍵となります。たとえば、公開する技術の範囲や利用できる分野、改変や再許諾の可否、さらにはライセンス期間など、細やかなルール設定が必要です。
「医療分野限定で利用」「期間を区切ったライセンス提供」「第三者への再許諾は禁止」といった条件を設けることで、自社の知財や利益を守りながら、信頼できるパートナーとの協業が実現できます。
ガバナンスは“契約書”という形式面だけでなく、日々の運用やパートナーとの信頼構築、情報のモニタリング体制にも関わってきます。
オープンクローズ戦略は、ただの技術戦略ではありません。
それは、「市場をどう支配し、利益をどう得るか」というビジネス全体の設計です。
Apple、三菱電機、IBMのように、成功している企業は「開放と囲い込み」を絶妙に使い分けています。あなたの会社でも、以下のステップで導入を検討してみてください。
この戦略は、一朝一夕でできるものではありません。
ですが、丁寧に設計し、社内に浸透させれば、大きな武器になります。
今こそ、あなたのビジネスに「開放」と「囲い込み」の視点を。「普及も利益もあきらめない」戦略で、競争優位を築いていきましょう。
この記事を執筆した人

長尾 浩平
新規事業創出や事業戦略の専門家として、多様な業界での経験を持つコンサルタント兼起業家。
東京工業大学大学院 生命理工学研究科、および中国・清華大学大学院 化学工学科を卒業。グローバル企業において研究開発、新規事業企画、新市場参入戦略の立案、M&A支援、DXコンサルティング、営業戦略策定など、多岐にわたる業務を担当。業界を横断した豊富な経験を活かし、事業成長と競争力強化を支援する総合コンサルティングを提供。
2024年1月にVANES株式会社を創業し、企業の持続的成長を支援。変化の激しい市場環境において、戦略立案から実行支援まで一貫したアプローチで企業価値の最大化に貢献している。
人気記事
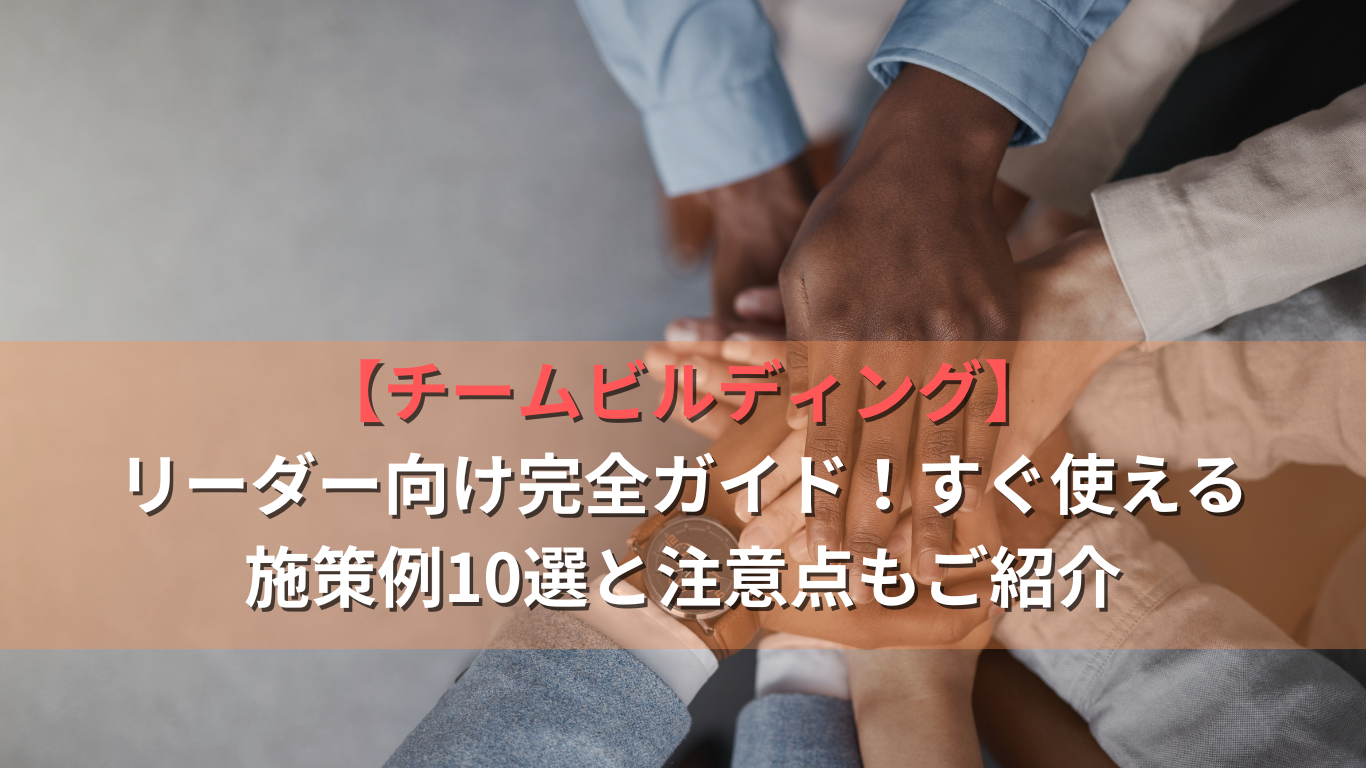
プロフェッショナル人材をお探しなら|2025.07.02
チームビルディングって何?チームをまとめたいけれど、何をどう始めればいいの? リーダーになってチームをまとめる必要が出てきたけど、...
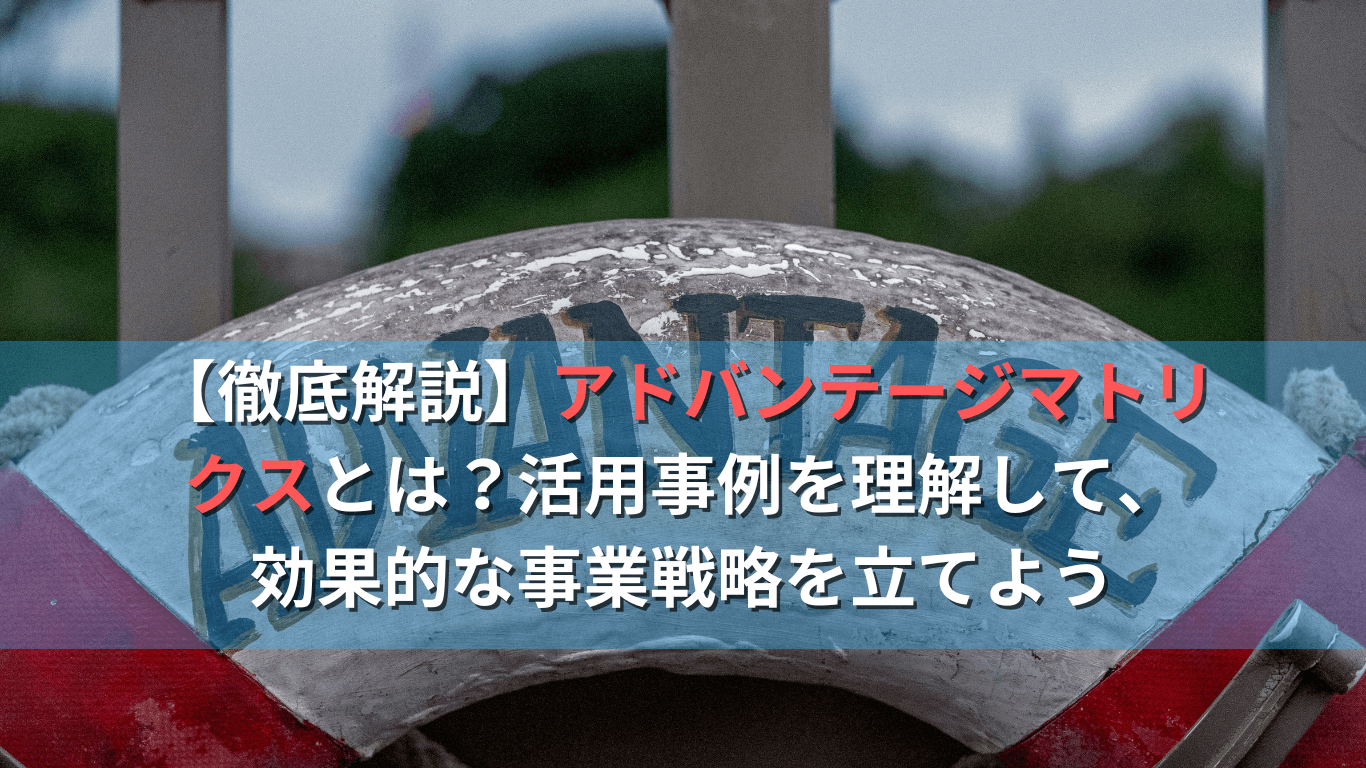
プロフェッショナル人材をお探しなら|2025.05.22
BCGが開発したっていわれているアドバンテージマトリクスって聞いたことはあるけど、どういうものなの?どうやって使うのか知って、業務...
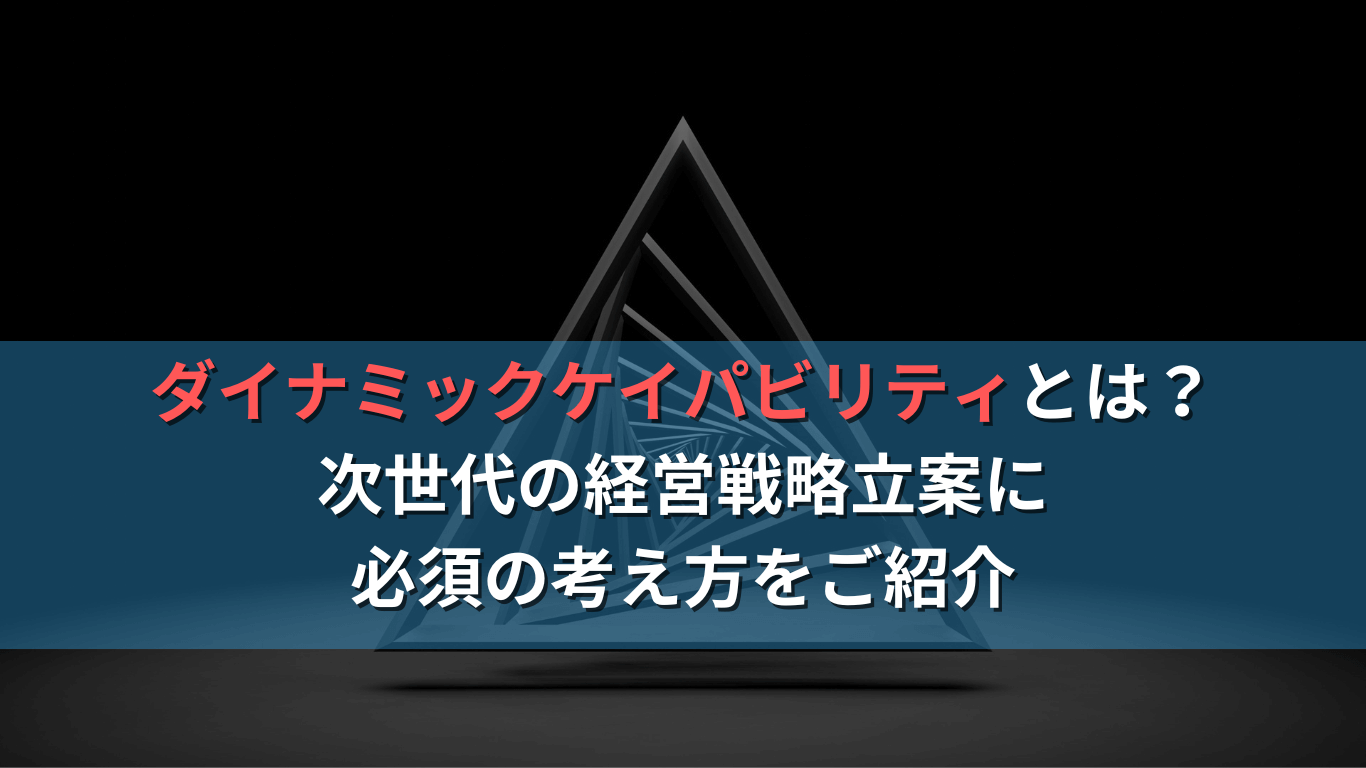
プロフェッショナル人材をお探しなら|2025.05.22
ダイナミックケイパビリティって何に使えるの?経営理論っぽいけど、具体的にどう活かすの? 不確実な時代に「変われる力」がある社員や企...
カテゴリー