プロフェッショナル人材をお探しなら|2025.07.02
【チームビルディング】リーダー向け完全ガイド!すぐ使える施策例10選と注意点もご紹介
チームビルディングって何?チームをまとめたいけれど、何をどう始めればいいの? リーダーになってチームをまとめる必要が出てきたけど、...
Magazine
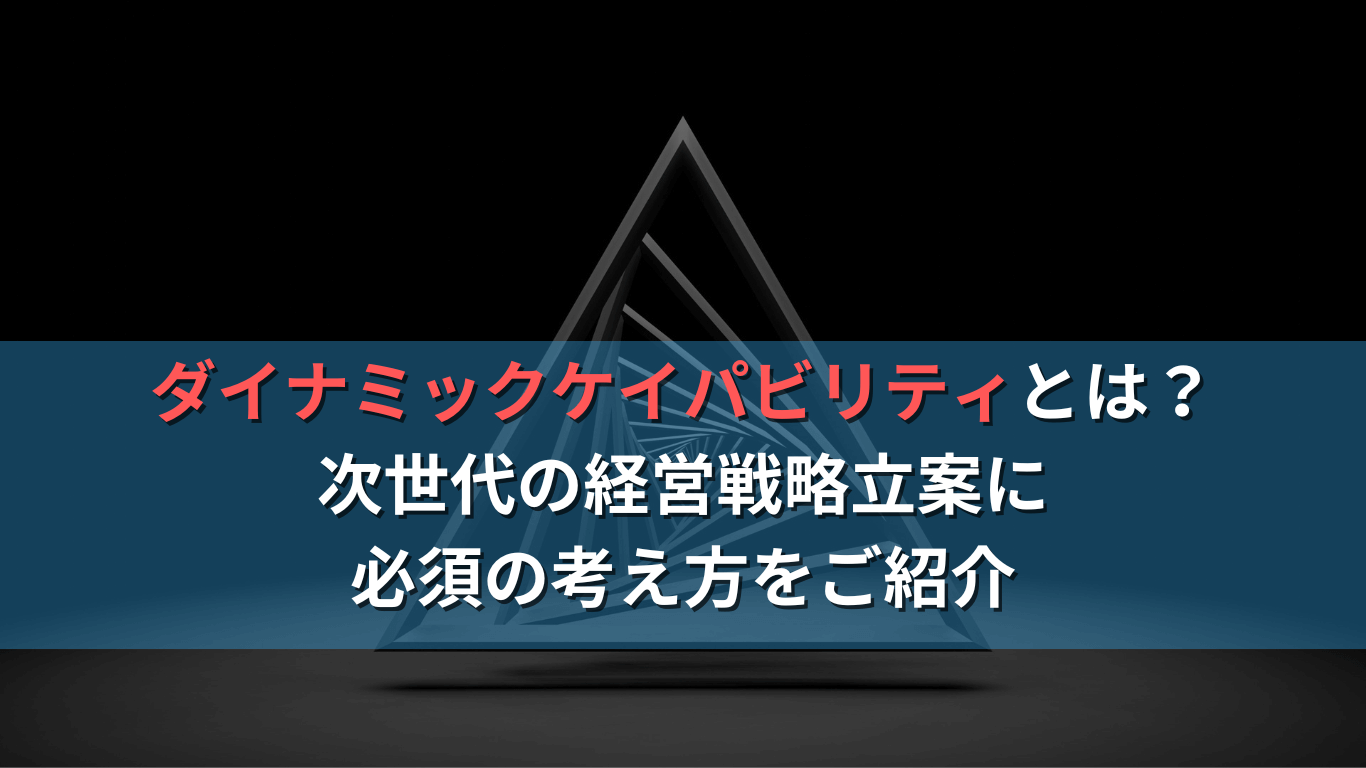
プロフェッショナル人材をお探しなら
2025.05.22
ダイナミックケイパビリティって何に使えるの?経営理論っぽいけど、具体的にどう活かすの?
不確実な時代に「変われる力」がある社員や企業は強いですよね。しかし、その変われる力の源泉を知らずにいると、競争の土俵にすら立てないかもしれません。
今回はダイナミックケイパビリティの概念・実務応用・成功事例について紹介します!必ず自分の視野を広げられる概念となっておりますので、是非この記事を参考に、自分の業務にも取り入れてみて下さい。
この記事で分かること!
弊社サービスNewAceは、あなたのチャレンジを応援するコンサルタントの方向けのプラットフォームです。
案件のご紹介のほか、様々な相談も承っておりますので、是非下記よりご登録ください。

それでは、本章をチェックください。
目次
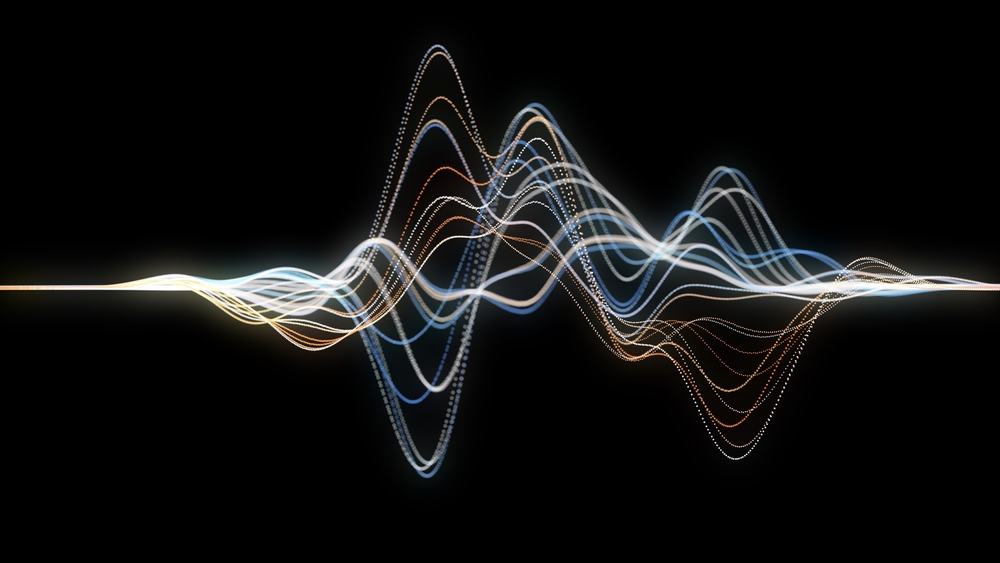
ダイナミックケイパビリティは、「変化の激しい環境でも企業が競争優位を維持・創造できる組織能力」です。従来型の経営資源や業務スキルとは異なり、時代や市場の変化に柔軟に適応し、継続的な成長や事業変革を実現するための力として注目されています。
イノベーションが求められる現代、ダイナミックケイパビリティを持つ組織こそが、長期的な競争優位を築くことができます。ここでは、その定義や基本的な考え方、従来の組織能力との違いについて分かりやすく解説します。
ダイナミックケイパビリティとは、「企業が環境変化を感知し、迅速に新しい価値創出へとつなげるための“変革力”」です。単なる効率化や日常業務の遂行力ではなく、「新しい資源の獲得・活用・再構築を繰り返し実行できる力」を指します。
たとえば、新規事業への参入や、コア技術の転換、急な市場変化にも「変わる力」と「伸ばす力」を発揮できるのが特徴です。
競争環境が激しい現代、ダイナミックケイパビリティは大手・中小問わずすべての企業に必須の能力となっています。
オーディナリーケイパビリティは、「日常的な業務遂行や既存事業の効率化に必要な組織能力」です。ダイナミックケイパビリティは、その上位にある「変化対応力」や「持続的な革新力」を意味します。
たとえば、同じ製造業でも、安定生産や品質管理はオーディナリー、AIや新素材導入によるビジネスモデル転換はダイナミックケイパビリティの領域です。
環境変化が少ない時代はオーディナリーだけでも十分でしたが、いまは「変わる力」なくして持続的な成長は望めません。

近年、企業がダイナミックケイパビリティを重視する背景には、社会やビジネス環境の大きな変化があります。
ここでは、なぜこの理論が現代経営に不可欠となっているのか、その背景を解説します。
近年、社会や技術の変化はかつてないスピードで進んでいます。新しいITやAI技術、サステナビリティへの対応など、どの業界でも「変化対応力」が重要な経営課題となりました。
たとえば、スマートフォンやクラウドの登場で通信・IT業界が一変したように、時代の波を捉えた企業だけが次の成長機会を手に入れています。
変化を先取りし、素早く組織を動かせる力が今、すべての業界で求められています。
グローバル市場の拡大とともに、企業が直面するリスクや不確実性も飛躍的に増加しています。
たとえば、同じ商品でも国や地域で求められる価値が異なり、事業展開やサプライチェーンも柔軟な見直しが必要になります。
「これまでのやり方」にとどまらず、絶えず組織や資源の組み換えを実行できるかが、競争力の分岐点となります。
消費者の価値観や購買行動も大きく変化しています。
たとえば、同じ業界でも「体験価値」「環境配慮」「即時性」など、重視されるポイントが年々変化しています。
これまで通りの事業運営では対応できないため、顧客の変化を敏感に察知し、迅速に戦略やビジネスモデルを変革できる力が不可欠です。

ダイナミックケイパビリティは、センシング(感知)・シージング(捕捉)・トランスフォーミング(変革)の3つの要素から成り立ちます。この3要素をバランス良く高めることが、変化対応力と持続的成長の鍵となります。
ここから、それぞれの役割や強化ポイントを具体的に解説します。
センシングは、「外部・内部の変化やチャンスを素早くキャッチする力」です。
たとえば、顧客からの問い合わせやクレーム、業界イベント、ベンチャーの動きなどに敏感な企業ほど、次の事業機会を見逃しません。センシング力が高いほど、時代の波を先取りできます。
シージングは、「察知した変化や機会を、具体的な戦略や事業に落とし込む力」です。
たとえば、新技術や市場トレンドを捉えて新商品やサービスをすばやくローンチできる企業は、シージングが強いと言えます。
情報をチャンスに変え、すぐ行動につなげることが重要です。
トランスフォーミングは、「既存の組織・事業・資源を抜本的に再構築する力」です。
たとえば、主力事業の成長が鈍化した際に、スピーディーに新しい分野にシフトしたり、デジタル化やDXを推進できる企業は、トランスフォーミング力が高い証拠です。
「変える力」が企業の生き残りと成長のカギを握ります。
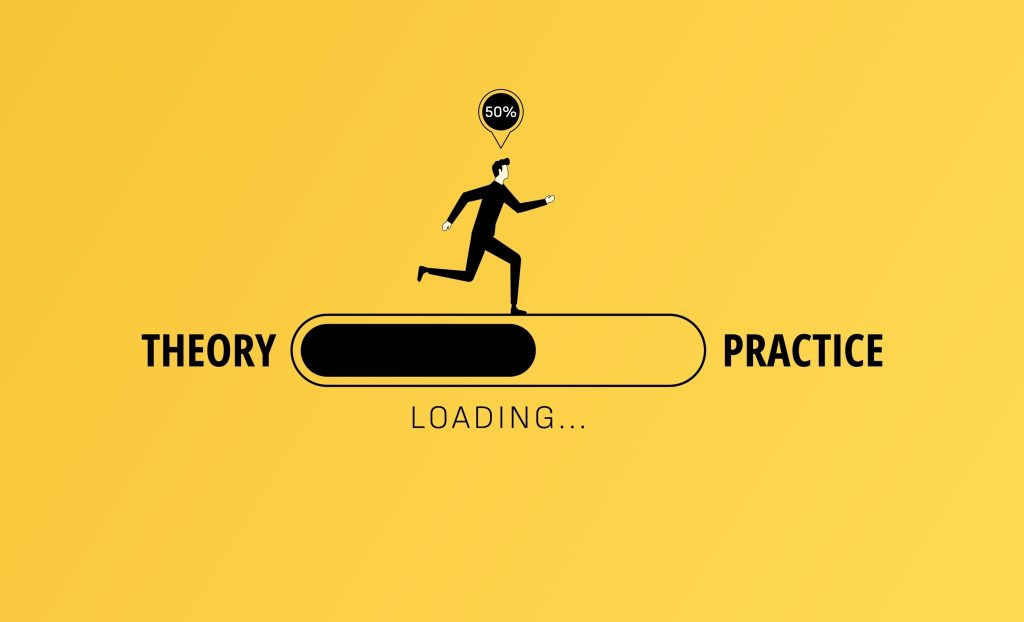
ダイナミックケイパビリティは、経営戦略論や経営資源の新しい捉え方と深く関係しています。
理論的な背景を知ることで、実務への応用やフレームワーク活用の幅が広がります。
ダイナミックケイパビリティは、従来の「ポジショニング型競争戦略」では捉えきれない環境変化やイノベーション対応を重視した理論です。
たとえば、業界構造が変わる時代は、ポジショニングだけでは競争力を維持できません。企業は自ら「強みや資源」を組み換え、時代ごとに競争軸をアップデートする必要があります。
資源ベース理論は、「企業独自の資源や能力が競争優位の源泉」とする考え方です。ダイナミックケイパビリティは、資源ベース理論をさらに発展させ、「資源を絶えず再構築・再活用できる能力」に注目しています。
たとえば、製造技術やブランドなどの既存資源を、AIやデジタルの力で新たな市場や価値創出につなげるのがダイナミックケイパビリティの典型例です。

ダイナミックケイパビリティは、DX(デジタルトランスフォーメーション)時代の経営においても極めて重要です。
デジタル化による環境変化に柔軟かつ持続的に適応できるかどうかが、企業存続と成長の分岐点となっています。
DXは、「デジタル技術を活用し、ビジネスモデルや業務プロセスを抜本的に変革すること」を意味します。
たとえば、製造業がIoTやビッグデータで新しいサービス収益を生み出したり、小売業がリアルとデジタルを統合した新たな顧客体験を提供するなど、DXは全業種で進行中です。
DX推進の成否は、企業のダイナミックケイパビリティ次第と言っても過言ではありません。
たとえば、紙ベースの業務や旧来型の意思決定を、デジタル起点に切り替えられるかどうかは、組織全体の「変革力」にかかっています。DXは「変わる力」を企業文化として根付かせるプロセスであり、その原動力がダイナミックケイパビリティなのです。
ダイナミックケイパビリティを高めるには、理論だけでなく現場の課題や実装面の注意点にも目を向ける必要があります。
ここでは、導入や運用時に直面しやすい課題とその対策ポイントを解説します。
変革には時間・人材・資金などのリソースが不可欠ですが、多くの企業がリソース制約という壁に直面します。
たとえば、新しい分野やDX投資に思い切って資源を振り向けられるかどうかは、経営層の意思決定と組織の覚悟にかかっています。
環境変化に対応するためには、多様なスキルや経験を持つ人材が不可欠です。
たとえば、IT人材不足や新技術への対応遅れが、企業の変革力を大きく左右します。
人材戦略を経営の最重要テーマとして位置付け、積極的な採用・育成・外部活用を進める必要があります。
未来を正確に予測し、即座に適応できる組織づくりは簡単ではありません。
たとえば、市場や技術の変化を正確に捉え、柔軟に戦略転換できる仕組みづくりが不可欠です。
経営層が率先して危機感と変化対応力を示すことで、組織全体が柔軟性を高められます。

ダイナミックケイパビリティは、実際の企業変革や競争優位の実現に大きく貢献しています。
ここでは、代表的な日本企業の具体的な成功事例を解説します。
富士フイルムは、写真フィルム市場の急激な縮小をいち早く察知し、事業構造を大きく変革しました。
たとえば、写真用フィルムの技術を活かし、ヘルスケアや高機能素材など複数の新事業を創出。
時代の変化に適応したダイナミックケイパビリティの実践例です。
ダイキンは、グローバル化と技術革新を同時に推進し、世界トップレベルの空調メーカーへと成長しました。
たとえば、現地化戦略と技術革新を両立し、市場ごとに最適な商品・サービスを展開。
変化する市場ごとに資源と組織を再構築できる力が強みです。
Hondaは、時代や市場の変化に合わせて製品・技術・組織体制を柔軟に変革し続けています。
たとえば、エンジン技術の強みを活かしつつ、電動化や次世代モビリティ分野にも果敢に挑戦。
Hondaの変化対応力は、ダイナミックケイパビリティの実例といえます。
ダイナミックケイパビリティを組織で実践し、強化するには明確な戦略が必要です。
ここでは、企業が変革力を高めるために押さえるべき具体的な戦略ポイントを紹介します。
経営層が時代の変化やリスクを敏感に察知し、迅速かつ柔軟に意思決定できるかが成否を分けます。
たとえば、トップ自らが危機感を示し、リスクテイクを現場に後押しする姿勢が、全社の変革力を高めます。
組織全体が変化や新しい知見を取り入れやすい構造にすることが重要です。
たとえば、柔軟な組織再編や新規事業チームの設置により、外部環境への対応力が強まります。
事業や組織の変革には、既存資源の再配分や新規投資の最適化が不可欠です。
たとえば、非中核事業からの撤退や資源の再配分を決断できる企業は、変化対応力が高まります。
将来の成長に向けた資源の柔軟な再設計が、ダイナミックケイパビリティの土台です。
ダイナミックケイパビリティは、不確実性の高い現代において最も重要な組織能力の一つです。変化を恐れず、チャンスを見抜き、自ら事業や組織を変革できる力が持続的な競争優位を生み出します。
たとえば、現場から経営層まで「変化を歓迎する」姿勢が、全社の成長エンジンとなります。
ダイナミックケイパビリティを活かすには、理論と現場実践の両輪が不可欠です。
たとえば、「現場の声を経営判断に即反映できる体制」「小さな変化を大きな変革へつなげる仕組み」が組織に根付くことが重要です。
この記事を執筆した人

長尾 浩平
新規事業創出や事業戦略の専門家として、多様な業界での経験を持つコンサルタント兼起業家。
東京工業大学大学院 生命理工学研究科、および中国・清華大学大学院 化学工学科を卒業。グローバル企業において研究開発、新規事業企画、新市場参入戦略の立案、M&A支援、DXコンサルティング、営業戦略策定など、多岐にわたる業務を担当。業界を横断した豊富な経験を活かし、事業成長と競争力強化を支援する総合コンサルティングを提供。
2024年1月にVANES株式会社を創業し、企業の持続的成長を支援。変化の激しい市場環境において、戦略立案から実行支援まで一貫したアプローチで企業価値の最大化に貢献している。
人気記事
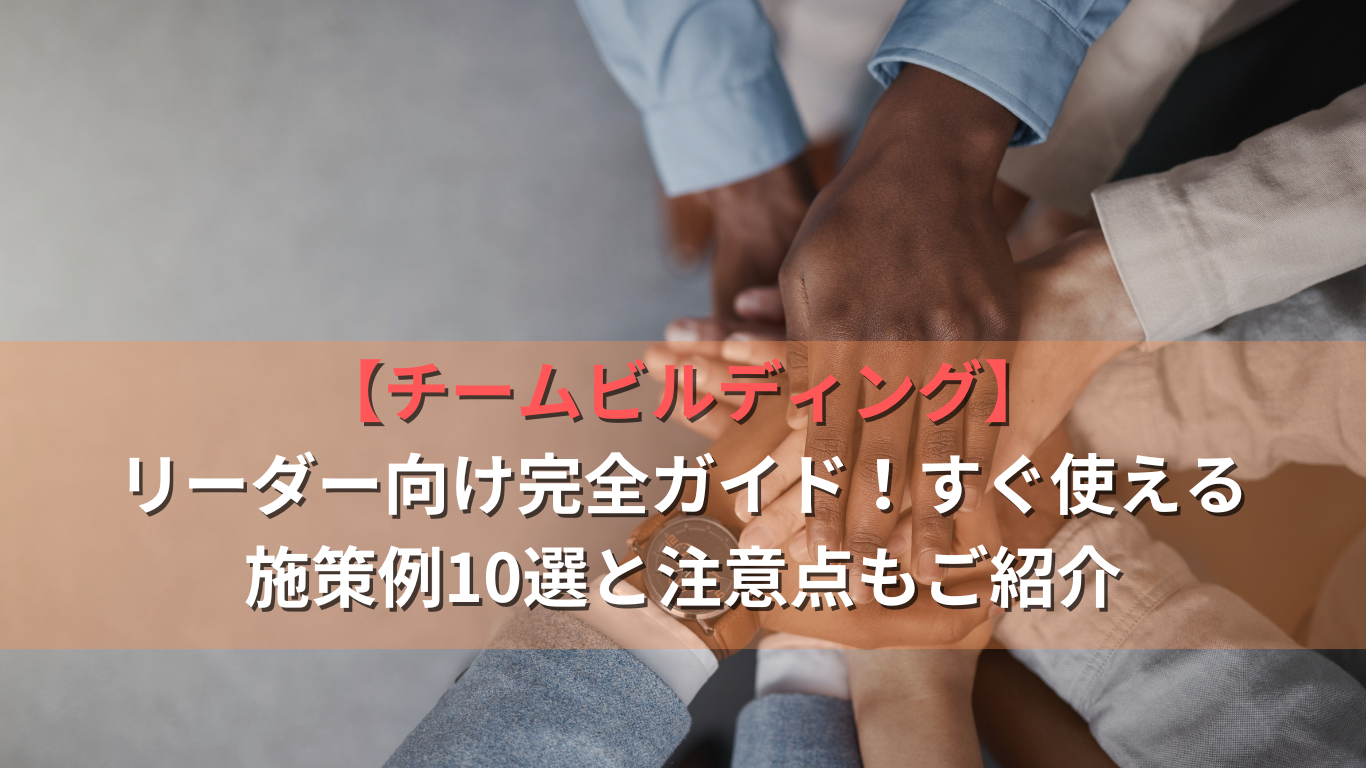
プロフェッショナル人材をお探しなら|2025.07.02
チームビルディングって何?チームをまとめたいけれど、何をどう始めればいいの? リーダーになってチームをまとめる必要が出てきたけど、...

プロフェッショナル人材をお探しなら|2025.05.22
オープンクローズ戦略って、実際どう使うの?任天堂やAppleがうまく使っているって聞いたけど… 自社のサービスについて、何をオープ...
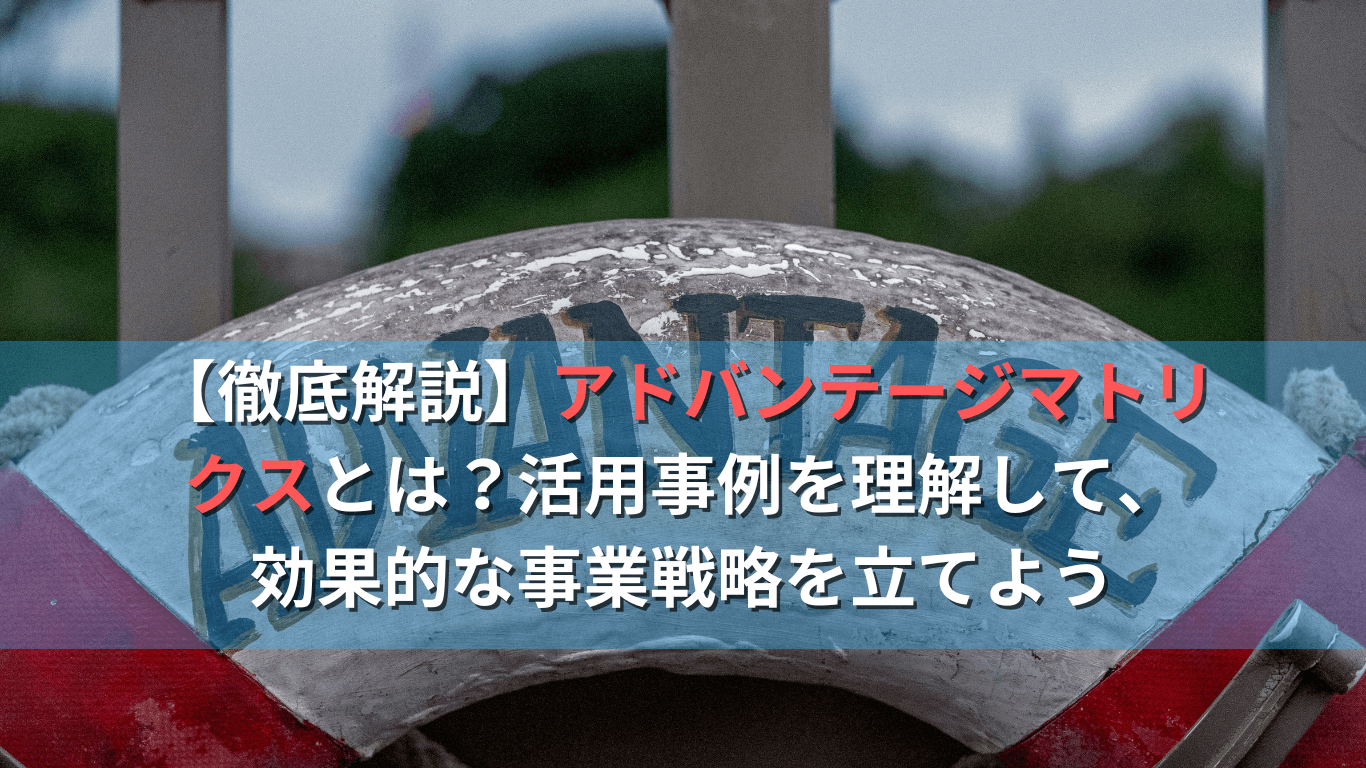
プロフェッショナル人材をお探しなら|2025.05.22
BCGが開発したっていわれているアドバンテージマトリクスって聞いたことはあるけど、どういうものなの?どうやって使うのか知って、業務...
カテゴリー