フリーコンサル独立準備ガイド|2025.05.27
フリーコンサルとして独立後の法人化のタイミングは?節税メリットを最大化する方法
フリーコンサルを始めて、このまま個人事業主でいるべきか、法人化に踏み切るべきか?法人化ってひとりしか社員がいなくてもできるの? フ...
Magazine
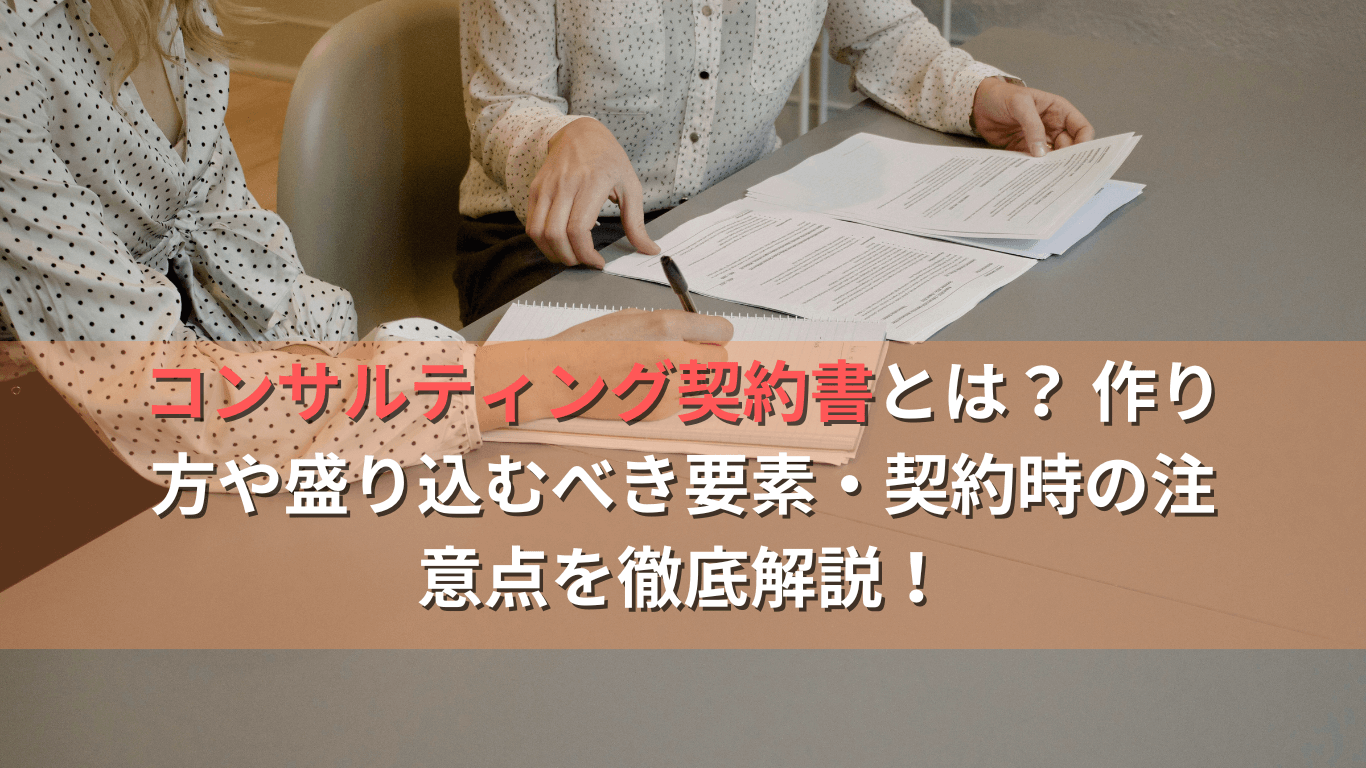
フリーコンサル独立準備ガイド
2025.05.22
フリーコンサルで案件に参画する際、契約書にサインしたけど、そもそもコンサルティング契約書ってどんな書類?あまり読まずにサインしたけど、後で何かないか不安…
フリーコンサルで案件参画時には、契約を締結すると思いますが、あまり詳細まで見て判断するということは難しいですよね。しかし、その契約の内容次第で報酬や責任が変わってくるので、注意が必要です。内容が曖昧のまま契約書にサインすると、損失やトラブルを招くかもしれません。
今回はフリーコンサルが契約を結ぶ際に気にするべき情報に着目して紹介します!コンサルティング契約書の基本構成や記載例、注意点など、契約に馴染みのない方に対してわかりやすく解説します。この記事を参考に、契約締結時に見るべきポイントを掴みましょう!
この記事で分かること!
弊社サービスNewAceは、あなたのチャレンジを応援するコンサルタントの方向けのプラットフォームです。
案件のご紹介のほか、様々な相談も承っておりますので、是非下記よりご登録ください。

それでは、本章をチェックください。
目次

フリーランスのコンサルタントが企業と結ぶ契約には、専門知識や助言を提供する内容が含まれます。成果が形に見えにくい業務だからこそ、契約書で役割や範囲を明確にする必要があります。
こうしたポイントを理解すれば、トラブル回避だけでなく、安心して長期的な関係を築けます。
コンサルティング契約とは、クライアントに専門知識やノウハウを提供するための業務契約です。コンサルタントは、経営改善や新規事業開発など、経営の重要な部分を支援しますが、助言や分析といった成果は、目に見えるモノではありません。そのため、成果物の定義が曖昧だと、トラブルになることもあるため、契約書で内容を定義します。具体的には以下のような内容が契約に含まれます。
契約書にこうした情報を記載することで、後から「そんな話は聞いていない」と言われるリスクを減らせます。
コンサルタントの仕事は、成果物が「モノ」ではなく「情報」や「助言」です。モノとして形が残らないサービスだからこそ、契約で責任や範囲を明記しなければなりません。
理由は以下の通りです。
たとえば「マーケティング戦略の提案」を依頼された場合でも、「いつ」「どこまで」「どういう形で」といった条件が不明瞭だと、後で揉めます。「追加料金は払えない」と言われたり、「成果が思ったものと違う」とクレームになることも。逆に契約書があると、どこまでが業務範囲で、どの条件下で追加料金が必要かがはっきりして、より良い関係を長期で築ける土台になるのです。
「フリーでやっているからこそ、契約書で自分の身を守る」
これがフリーコンサルとして生き残るために必要な姿勢だと言えます。コンサルティング契約とは、専門的な知識や助言を提供する業務に関する契約です。多くはフリーランスや外部のコンサルタントが企業と結びます。
次に、コンサルティング契約がもたらす具体的なメリットを解説します。

フリーコンサルタントが仕事を始める時、契約を結ぶことは絶対に欠かせません。契約書があることで、自分の立場や守るべきルールが明確になります。
こうしたメリットを知らずに契約せず仕事を始めてしまうと、大きなトラブルになるリスクが高まります。「契約が面倒」「契約書を読むのが苦手」と感じている方も多いですが、契約書をしっかり確認することは自分を守るための第一歩です。
ここからは、フリーコンサルが契約書で特に押さえておきたい目的と、そのメリットについて順番に説明します。
契約書を作成すると、自分がどこまで対応するのかをハッキリ示せます。責任範囲を言葉で済ませるのはトラブルのもとです。書面で決めておくことで後から言った言わないの揉め事を防げます。
たとえば、「コンサルティング」とひとことで言っても、実は内容がとても広いです。提案までなのか、実行サポートも含むのか、資料作成はどこまでか、報告の方法はどうするのかなど、細かい部分まで契約書に記載します。
以前、業務範囲を曖昧なまま契約した結果、クライアントから「この調査もやってほしい」「追加で会議も頼む」と依頼が増えてしまった経験があります。書面で「実施する業務範囲」を具体的に明記していれば、追加依頼に対して「契約外です」としっかり伝えることができます。
自分の身を守るためにも、責任範囲の明確化は必ず意識しましょう。
契約書では、具体的にどんな業務を行うのかを書きます。「どこまでが契約内容なのか」を明記することで、余計な仕事や無茶な要求を避けられます。
「週1回の打ち合わせ」「月次レポートの提出」「提案書の作成」といった具体的な内容を細かく記載します。これにより「やるべきこと」「やらなくてよいこと」が両者で一致します。
業務内容をざっくり書いた契約で、クライアントから「もっと頻繁に打ち合わせしたい」と言われたことがありました。その時は追加で費用が発生することを納得してもらえず、結果報酬に見合わない労働になったというものです。
しっかり定義することで、お互いに納得した形で仕事を進められます。
契約書を交わすことで、支払のタイミングや方法を明確にできます。万が一、支払が遅れた時やトラブルが起きた時にも契約書が証拠になります。
たとえば、「月末締め翌月末払い」「成果物納品後7日以内に振込」といったルールを書きます。
契約書に支払期日を明記しなかった案件で、報酬が2ヶ月以上遅れたという方がいました。必ず「いつまでに」「どの方法で」支払われるかを細かく記載されているか確認しましょう。「支払いが遅れる」「振込先が間違っていた」といった細かいトラブルも、契約書をもとにスムーズに解決できます。
コンサルタントとして、契約の目的とメリットをしっかり押さえておけば、トラブルを防ぎ、安心してプロの仕事に集中できます。

コンサルティング契約には複数の種類があります。目的や業務の内容によって、適切な契約形態を選ぶ必要があります。
契約形態によって、コンサルタントとクライアントの責任範囲は大きく変わりますので、この章では、フリーコンサルでよく使われる契約形態を比較しながら解説します。
コンサルティング業務では、主にこの3つの契約が使われます。それぞれの特徴を理解して、適切に選ぶことが重要です。
| 委任契約 | 準委任契約 | 請負契約 |
| 法律行為を代行する契約 | 事務や業務の遂行を任せる契約 | 成果物の完成を約束する契約 |
コンサルティングで最も多いのは「準委任契約」です。たとえば「月に1回のアドバイス提供」や「会議への参加」は準委任契約に該当します。逆に「事業計画書の作成」など、具体的な成果物を納品する場合は請負契約になります。
一方、弁護士などが契約書を作成する際の代理行為は「委任契約」にあたります。契約形態の誤りは、後のトラブルの元になりますので、自分の業務に合った契約を選べるようにしておきましょう。
アドバイザリー契約や顧問契約も、コンサルティングと重なる場面が多くあります。しかし、目的や契約内容には微妙な違いがあります。
アドバイザリー契約は、M&Aや投資の分野で多く使われます。たとえば、事業売却の過程でファイナンシャルアドバイザーをつける場合などです。
顧問契約は「何かあったらすぐに相談できる」体制を整える目的があります。契約期間が長く、業務範囲も曖昧になりがちです。そのため、顧問契約の場合は「対応時間の目安」や「相談範囲」を契約書で明記することが重要です。
このように、契約の目的や関係性によって内容は大きく変わります。言葉に惑わされず、「何をする契約なのか」で判断しましょう。
フリーランスのコンサルタントは、業務委託契約を結ぶことがほとんどです。業務委託契約は、会社と雇用関係を持たずに業務を任せる契約です。業務委託契約には、先ほど説明した「準委任」や「請負」が含まれます。
| 雇用契約 | 業務委託契約 |
| 指示命令関係あり、労働法が適用 | 独立した立場、自己責任 |
たとえば、スタートアップで「社外CMO」として支援する場合、毎月戦略提案を行い、必要に応じてチームとも連携するという内容になったとします。このような場合は準委任契約+業務委託契約になります。
注意すべきは、契約の内容が曖昧だと「偽装請負」や「雇用関係の誤認」に発展する点です。業務委託契約を結ぶ際は、指揮命令を避け、契約書で独立性を明記する必要があります。
フリーランスとして信頼されるには、契約の正確さが大切です。書類が整っていれば、企業側も安心して仕事を任せられます。
次は、コンサルティング契約が実際に使われる代表的な場面を紹介します。

コンサルティング契約は、さまざまな場面で活用されています。企業の課題解決や新たな挑戦を支えるために必要不可欠です。
ここでは、実際にコンサルティング契約がよく使われる2つの代表的なシーンを紹介します。
企業の経営課題に取り組む場面で、コンサルタントの支援は重要です。特に「新規事業」や「売上改善」では外部視点が大きな武器になります。
たとえば、地方の製造業が「ネット販売を始めたい」と考えたとします。社内にECやマーケティングの知識がない場合、外部のコンサルタントを活用するのが効果的です。
このような業務には専門知識が求められるため、契約内容も明確にしておく必要があります。「どこまで支援するのか」「実行は含むか」などを契約書で整理することが重要です。特に新規事業では、想定と現実にギャップが出やすく、契約の見直しが頻繁に行われます。
契約期間や変更条件について、柔軟な条項設計も求められます。
このように、独立して新規事業の支援をしたいけど、契約周りで不安という方については、弊社NewAceのサービスの活用も視野に入れてみてください。責任の所在はしっかり分けて契約締結しますので、安心して業務に参画いただけます。

M&Aや財務戦略の支援でも、コンサルティング契約は重要な役割を果たします。これらの業務は高度な専門性と守秘義務が必要だからです。
たとえば、ある中小企業が「事業承継で売却を検討している」とします。その際、M&A仲介業者や財務コンサルタントと契約を結びます。契約では次のような点を明記する必要があります。
また、買収交渉が長期化する場合、追加報酬が発生するケースもあります。そうした場合も含めて、報酬の支払い基準を明記することが求められます。M&Aでは内部情報が多く関わるため、「秘密保持条項」が非常に重要です。破った場合の罰則や期間の設定も、契約書でしっかり規定します。
このように、高度な意思決定に関わる場面では、コンサルティング契約が不可欠です。専門家の知見を活かすには、契約内容を適切に整えることが第一歩となります。
次は、実際の契約書にどのような項目を盛り込むべきかを詳しく解説します。

契約書は、ただ形式を満たすだけのものではありません。実務に即した具体性があることで、トラブルを未然に防げます。
ここでは、コンサルティング契約で頻出する主要条項を解説します。
最も重要な条項のひとつが「契約の目的」と「業務内容」です。この内容が曖昧だと、後々のトラブルにつながります。
たとえば「経営改善に関する助言業務」と記載するだけでは不十分なので、具体的にはこう記述します。
クライアントが実施する新規事業立ち上げに伴う、戦略立案・市場調査・会議出席等の支援業務
業務内容に抜け漏れがないよう、箇条書きにするのが望ましいです。また、「成果を保証しない」旨もここで明記するケースが多いです。
報酬は「いくらもらうか」だけでなく、「いつ・どうやって払うか」も重要です。
を記載します。記述例は、
月額30万円(税抜)を毎月末締め翌月末支払にて、指定口座に振り込むものとする
また、経費精算がある場合は、その範囲と上限を明記します。「交通費は実費支給」「月2万円まで」などがよく見られる記述です。
資料や成果物に関する権利関係も明確にしておくべきです。
たとえば、
資料の著作権はコンサルタントに帰属し、クライアントは業務目的に限り使用可
とすることもあります。逆に「納品と同時にすべての権利を譲渡する」ケースもあります。事前に合意がなければ、後でトラブルになる可能性が高い条項です。
契約の始まりと終わり、途中終了の条件も必ず書きましょう。
一般的な記述は次のようになります。
契約期間は2025年6月1日から2025年11月30日までとし、いずれかが1か月前までに書面で更新拒否を通知しない限り、自動で6か月延長する
途中解約に関しては「30日前通知」や「即時解除」の条件もセットで記載します。トラブルを避けるには、曖昧な表現を使わないことが大切です。
機密情報の扱いは、多くの企業が特に重視します。
守秘義務の書き方としては、
契約終了後も5年間、本契約に関連して知り得た一切の情報を第三者に開示・漏洩しないこと
本契約期間中および終了後1年間、同業他社の案件に関与しないこと
ただし、制限が強すぎると契約自体を避けられることもあるため、実務に即したバランスが求められます。再委託についても、外注する場合の許可条件や責任範囲を定めます。
万が一のリスクに備える条項で、フリーコンサルにとっては最も注意が必要な箇所かもしれません。
損害賠償の記述例と、反社条項の記述例はそれぞれ下記になります。
「甲乙いずれも、本契約に関連して相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に発生した通常損害に限り、金◯万円を上限として賠償する」
「相手方が反社会的勢力に該当すると判明した場合、何らの催告を要せずに契約を解除できる」
どれも万一の事態に備える条項ですが、実務上は非常に重要です。このように、契約書には多くの要素が含まれます。

フリーコンサルが契約書を確認するとき、見落としがちな注意点がいくつもあります。特に損害賠償や業務範囲の曖昧さ、印紙税の扱いは要注意です。
こうしたポイントをチェックしないと、思わぬトラブルや余計な負担につながることもあります。どの項目も「第三者が見ても意味が明確」な内容になっているか確認しましょう。
コンサルティング契約で一番リスクになるのが損害賠償です。損害賠償の範囲や上限が書かれていないと、大きな責任を背負う可能性があります。
たとえば、「コンサルの提案で損失が出た」場合、契約書に何も記載がなければ無制限に損害賠償請求されるおそれがあります。一方、上限額が定められていれば、リスクはコントロールできます。実際に、損害賠償の条項が曖昧だった案件で「数百万円の損害」を請求されたコンサルタントの例もあります。
【記載する際の具体例】
損害賠償について不明点があれば、契約前に必ず相談・交渉しましょう。これだけで、後のトラブルを大きく減らせます。
契約書に多い落とし穴が「業務内容の曖昧な表現」です。解釈に幅が出る書き方だと、後から追加業務や期待外れが生まれやすくなります。
たとえば「助言を行う」「必要に応じて支援する」という文言は、どこまでやるべきか解釈が分かれやすいです。「どの程度」「誰が判断」「どんな手段」まで決めて書いておく必要があります。実際に「必要に応じて」という文言が原因で、「毎週ミーティング参加」を求められたトラブルもありました。
【記載する際の具体例】
第三者が見ても分かりやすい内容になっているか、必ず見直しましょう。これだけで、余計な仕事を断る根拠が生まれます。
契約書を作るとき「印紙税」の有無も大きなポイントです。フリーコンサルの多くは印紙税が不要ですが、成果物納品型や請負契約だと印紙が必要な場合もあります。
たとえば「納品物を作成し、完了時に報酬が発生する」と書いてあれば請負契約になり、収入印紙が必要です。一方で「アドバイス業務」や「定期的な支援のみ」なら印紙税はかかりません。
【記載する際の具体例】
印紙を貼り忘れても契約自体は無効になりませんが、後から税務署に指摘されると追徴課税のリスクがあります。「契約内容に成果物や納品書が含まれていないか」「報酬が成果物に紐づいていないか」を必ず確認しましょう。不安な場合は、専門家に確認すると安心です。
「契約書の損害賠償、業務範囲、印紙税の3点」は、フリーコンサルが特に気をつけるべき大切なポイントです。
コンサルティング契約は、信頼と責任を形にする手段です。また、しっかりとした契約書があれば、後悔やトラブルを防げます。
コンサルタント側もクライアント側も、「明文化された約束」があれば安心して業務に集中できます。あなたのビジネスを守るために、契約書は最も基本的で強力なツールです。
契約書がしっかりしていれば、信頼関係も深まります。契約は「もしも」のための備えではなく、「円滑な仕事」のための道具です。
この記事を執筆した人

長尾 浩平
新規事業創出や事業戦略の専門家として、多様な業界での経験を持つコンサルタント兼起業家。
東京工業大学大学院 生命理工学研究科、および中国・清華大学大学院 化学工学科を卒業。グローバル企業において研究開発、新規事業企画、新市場参入戦略の立案、M&A支援、DXコンサルティング、営業戦略策定など、多岐にわたる業務を担当。業界を横断した豊富な経験を活かし、事業成長と競争力強化を支援する総合コンサルティングを提供。
2024年1月にVANES株式会社を創業し、企業の持続的成長を支援。変化の激しい市場環境において、戦略立案から実行支援まで一貫したアプローチで企業価値の最大化に貢献している。
人気記事

フリーコンサル独立準備ガイド|2025.05.27
フリーコンサルを始めて、このまま個人事業主でいるべきか、法人化に踏み切るべきか?法人化ってひとりしか社員がいなくてもできるの? フ...
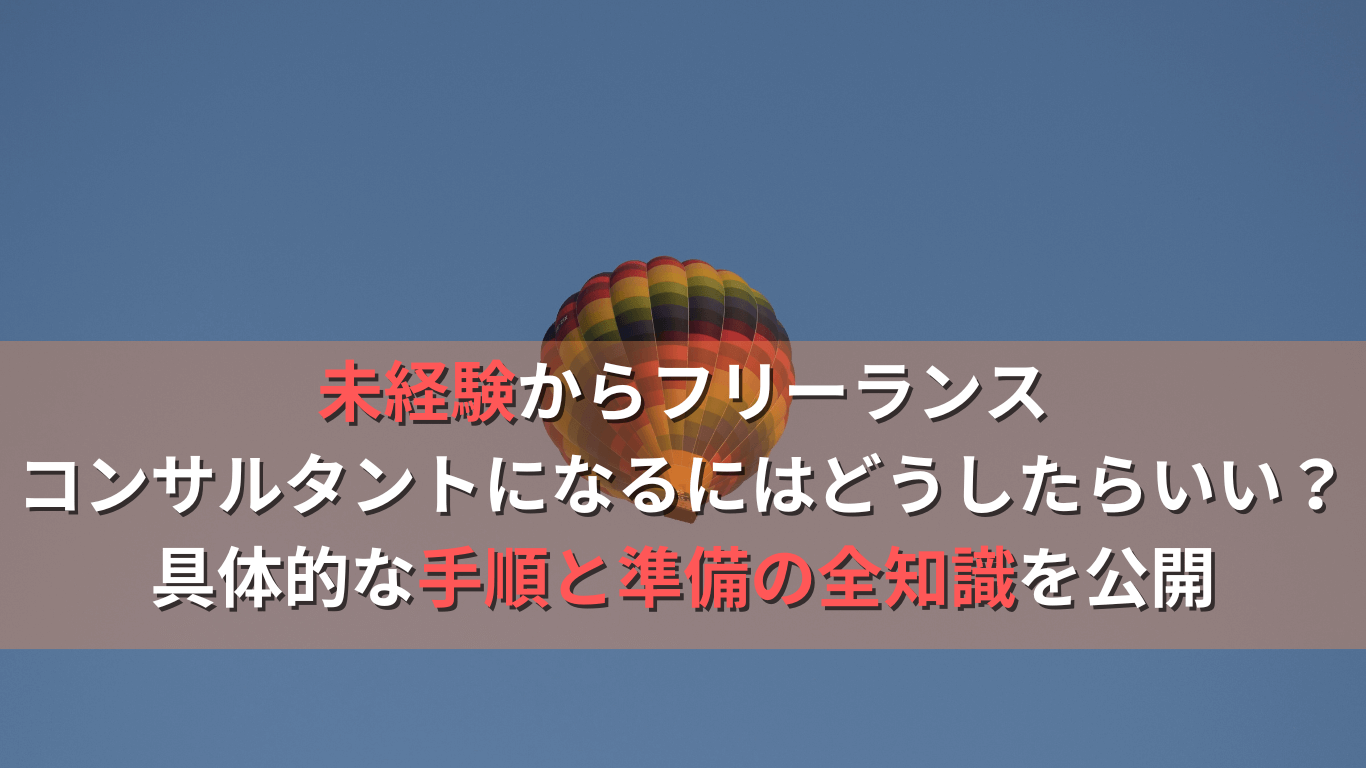
フリーコンサル独立準備ガイド|2025.05.22
どうすれば独立できるの?なるには何から始める? やってみたい気持ちはあるけど、何を準備してどう始めればいいか不安になりますよね。 ...

フリーコンサル独立準備ガイド|2025.01.09
「業務委託契約ってどう働くの?」フリーコンサルとして働くなら、業務委託契約の選択肢が気になるところ。メリットが多い一方で、契約内容...
カテゴリー